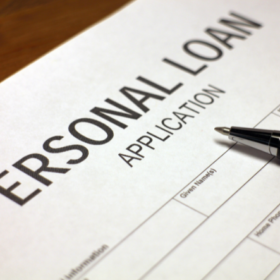どのようなビジネスを行うにしても、事業主が考える経営の維持と存続のためには、充実した資金調達が不可欠となります。
事業主が一番悩む点でもあります。
資金調達が必要になれば、多くの事業主の方が真っ先に銀行からの融資を検討するかと思います。
銀行融資は、低金利で長期間の借り入れが可能になるだけでなく、借り入れ先としての信頼性の高さも抜群です。
また、銀行からの借り入れに成功することは、事業主の持つ企業の社会的価値の向上にも直結するため、取引先や株主からの評価の上昇にもつながることでしょう。
そのため、資金調達における安心感の獲得と企業の社会的意義の確立のためには、銀行融資が最適な手段であるといえます。
しかし銀行融資は厳しい審査基準であることが常識となっているほか、多数の提出書類を用意・作成する煩わしさや実際に資金が入金されるまでの期間が長いこともネックとなります。
事業主が抱える事情や問題によっては、銀行融資の活用を断念せざるを得ず、事業主によっては他の資金調達法を選択する必要もあるかと思います。
では、銀行融資以外の資金調達法にはどのようなものがあるのでしょうか。
銀行融資以外の手段で資金を調達したいと考えておられる事業主の方々に知っておいてほしい資金調達法をご紹介していきます。
補助金と助成金
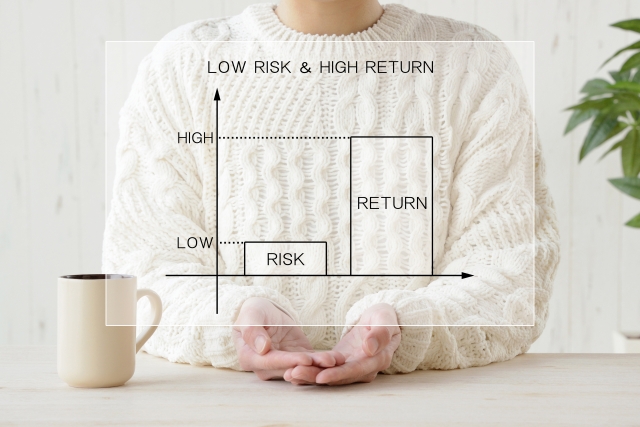
まずは、補助金と助成金です。
補助金と助成金は、どちらも資金の「借り入れ」ではないため、融資のように返済義務が生じることはなく、担保や保証人を用意する必要もないため、今回ご紹介する資金調達法の中でも最も低リスクの手段といえます。
つまり補助金と助成金は「もらえるお金」です。
事業主の方であれば、これら補助金と助成金という制度自体は知っているかと思いますが、2つの違いをきちんと理解できていますでしょうか?
補助金も助成金も支給元は国や地方自治体、民間団体であり、先述の通り返済の必要のない資金を取得できるという性質はどちらにも共通していますが、具体的な違いは以下のような点があります。
①補助金

主に経済産業省から支給される資金を補助金と呼びます。
補助金は、資金を税金から捻出し、国や各自治体が企業の新規事業や事業拡大、創業の促進など、何かしらの政策を達成する目的で支給されます。
支給額は、数百万円単位から申請する制度によっては数億円までを受給できる可能性がありますが、支給額の総予算はあらかじめ決められているうえ、申請期間が定められている公募制ですので早い者勝ちです。
また受給には審査も必要となるため、申請すれば必ず支給されるわけではありません。
ですので、公募が開始されればすぐにでも申請することが受給できるポイントとなりますが、事業計画書をはじめ多くの書類の提出や制度によっては面接が必要となる場合があるため、余裕をもって準備を進めなければなりません。
②助成金

一方、主に厚生労働省から支給される資金を助成金と呼びます。
設備投資費や原材料費の援助など、事業の発展促進や新規事業の開始など、事業を支援する目的で支給される補助金に対して、助成金は従業員のキャリアアップや雇用条件の安定、雇用の促進といった、主に雇用関係をサポートする支援金です。
助成金は補助金とは異なり、原則として年間を通して申請が可能です。
さらに、書類審査等はあるものの、支給元が提示する条件(業種や従業員数など)を満たしてさえいれば、ほぼ確実に受け取ることができる点も助成金の長所のひとつです。
ただし、支給額が大きいなどの理由で人気が集中する助成金は、支給条件の発表から数ヶ月で打ち切る場合もあるので、注意が必要です。
補助金よりも受給難易度が低く、比較的フレキシブルに申請できる助成金ですが、支給額は数十万円から数百万円のものがほとんどです。
補助金も助成金も、返済の必要がないという点では積極的に活用したい資金調達法といえます。
しかし、注意すべき点は受給が決定しても、すぐに支給されるわけではなく、使用した関係経費の申告後に現金を得られる点です。
実際の支給までの期間が長くなるため、急ぎの資金問題の解決には適していないかもしれません。
政府系金融機関からの融資

2つ目は政府系金融機関からの借り入れです。
政府系金融機関とは、政府が経済発展や国民生活の安定を目的に特殊法人として設立された金融機関です。
出資金の多く(または全額)を政府が出資しており、主な機関には国際協力銀行や商工組合中央金庫、住宅金融支援機構や日本政策金融公庫などがあります。
このうち、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫は中小企業への資金調達支援(普通貸付など)を行っているため、多くの事業主様にとって最も身近な政府系金融機関であるといえます。
融資を受けるには、民間の銀行融資と同様に審査が必要となりますが、銀行を補完する役割があることから、銀行融資を受けられない企業であっても、現状の経営状況や資金面だけでなく事業の将来性を評価するといった、柔軟な審査基準が設けられている点から、民間の銀行よりも借りやすいといえるでしょう。
クラウドファンディング

3つ目は近年、特に注目を集める資金調達法として度々話題になるクラウドファンディングです。
クラウドファンディングとは、アイデアやプロジェクトの実現のため、インターネット上で目標額を定めた上で不特定多数の人物から資金を募る手段です。
企業の知名度や事業規模などに左右されることなく、資金を調達できるため、創造性豊かな若い起業家や個人事業主などが、積極的に活用する傾向にあるようです。
クラウドファンディングには、単に資金を寄付するサービスもありますが、プロジェクトが成功した暁に資金の提供者に対して金銭や物品の見返りを条件とする手段もあり、利用者は利用する目的や目標金額に応じて選択することになります。
仕組みだけを聞くと単純な資金調達法だと思われがちですが、目標金額を獲得するためには、独創性や公共性の高いアイデアやプロジェクトが求められるため、簡単に資金を調達できる手段とは言い難いのが実情です。
ファクタリング

企業が抱える売掛債権を売却して資金を調達する手段がファクタリングです。
あくまで「債権の売却」による資金調達手段であるという性質上、最近では「借りない資金調達法」などと評され、融資を受けられない中小企業の事業主などから高い人気を得ています。
ファクタリングには、主にファクタリング会社と利用企業に加え、売掛先(取引先)の三社による契約の「三社間ファクタリング」と、ファクタリング会社と利用企業のみで契約を交わす「二社間ファクタリング」があります。
どちらも、売掛債権の売却という仕組みに変わりはありませんが、二社間ファクタリングには、売掛先にファクタリングの利用を知られることはないというメリットがあり、秘匿性を保ちたい企業にとっては嬉しい仕組みといえます。
また、ファクタリングは借り入れではないため、利息を伴う返済の必要はありません。ただし、利用の際には売却額や企業評価に応じた利用手数料が発生します。
特に2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングよりも高額の利用手数料が必要となることを覚えておきましょう。
ノンバンクのビジネスローン

最後にノンバンクのビジネスローンです。
ノンバンクのビジネスローンといっても、基本的な仕組みは銀行融資と変わりありません。
利率の低さや社会的信用度においては、銀行融資に軍配が上がりますが、ノンバンクのビジネスローンは、銀行融資に比べて圧倒的に審査スピードが早いため、つなぎの運転資金の確保や緊急の資金繰りの改善には最適な資金調達法です。
また、審査基準も低く設定されていることから、銀行融資の審査でマイナス要因となる問題や事情を抱えていても、比較的柔軟に対応することが可能となります。
融資額も、数万円から数億円まで対応する事業主も数多く存在するため、小口から大口まで、資金調達の目的に応じて融資額を選択することができます。
ただし、先述の通り利率は銀行融資よりも高くなります。ですので、利用の際には慎重かつ計画性のある返済プランを立てる必要があることを忘れてはなりません。
事業主様に知ってほしい銀行融資以外の資金調達法のまとめ
今回は全事業主様に是非知っていただきたい銀行融資以外の資金調達法をご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
これらの資金調達法を初めて耳にした事業主様、すでに聞いたことがある事業主様もこの記事を通して新たな気づきがあれば幸いです。
ご自身の状況と資金調達法を正しく知ることでよりよい資金繰り改善、事業拡大に役立てましょう。