一般的に、「倒産」というと赤字経営が引き起こす事態であるとイメージするものです。
しかし、収益を上げており経営状態が黒字であるにもかかわらず、倒産に至るケースもあります。
それが「黒字倒産」です。
その主な要因として考えられるのは現金不足。
帳簿上で、どれだけ収益が発生していたとしても、現金の不足が生じてしまうと会社は倒産の結末を迎える恐れがあるわけです。
今回は、黒字倒産の具体的な解説とともに、その回避方法などについても触れていきたいと思います。
目次
そもそも倒産とは?

黒字倒産について解説する前に、そもそも倒産とはどういうものなのでしょうか。
実は、「倒産」という言葉は大手信用調査会社のひとつである「株式会社東京商工リサーチ」が用い始めたものとされており、法律用語として定義されている言葉ではなく明確な基準が定められているわけでもありません。
また、「倒産」は「経営破綻」や「会社が潰れた」という言葉とほぼ同義語という認識で間違いではないともいえます。
ただし、東京商工リサーチでは「倒産」という言葉を使う状況について以下のような基準を設けているようです。
| ・会社更生手続き、民事再生手続き、破産手続き、特別清算といった法的整理手続きを申し立てた場合。 ・6ヶ月以内に2回の手形不渡りを起こし、銀行取引停止処分となった場合。 ・私的整理、内整理といった任意整理を開始した場合 |
つまり倒産は、企業や個人事業主が債務の支払いができなくなることによって、経済活動が継続不可に陥った状況のことを指す言葉だということになります。
黒字倒産とは?

「倒産」がどのような状況であるかが分かったところで、次は黒字倒産についての解説をしていきたいと思います。
「黒字倒産」は、端的にいえば収入が支出を上回っているのにもかかわらず倒産してしまうことであり、「赤字倒産」とはまったく逆の状況で倒産に陥ることを指します。
具体例としては以下のようなケースが挙げられます。
現金100万円を保有するとある金属加工会社が、B社から120万円で資材を調達し、200万円でC社へと納品。
この場合、C社からの入金がB社への支払いよりも先であれば問題なく支払えますが、逆の状況となれば現金不足により支払い不能となります。
したがって黒字倒産とは、利益を得ていながらも、現金不足が要因となって支払い不能に陥り、経済活動が継続不可となった状況のことであることが分かります。
黒字倒産が起きる要因

・手元資金の不足
黒字倒産が起きる1番の要因は、やはり現金化できる手元資金の不足でしょう。
日本の商取引は、一般的に掛取引で行われる場合がほとんどであるため、たとえ売掛金が発生したとしても、実際の入金日は1〜2ヶ月後となるものです。
その間に現金化できる手元資金を上回るような支払いが必要となれば、キャッシュフローはたちまち崩壊し、正常な経済活動もままならなくなります。
・過剰在庫を抱える
ふたつめは、商品の在庫管理が不十分となり、過剰在庫を抱えてしまうことです。
販売機会を見越した上で在庫不足は回避したいという気持ちは十分に理解できますが、手元資金に見合わないほどの在庫の仕入れを行えば、それだけコストが嵩むことは明らかですし、その分、黒字倒産のリスクが高まるものです。
・曖昧な資金管理
経理や財務が正確に行われておらず、経営者が資金の流れを正確に把握していなかったことが要因となって黒字倒産に至ったというケースはよくあります。
これは、特に個人事業主や規模の小さい中小零細企業などでよくみられるケースなのですが、共通するのは思いつきや無計画による資金運用がなされていたということ。
そのような曖昧な資金管理を続けていれば、いくら黒字経営を続けていても、いつの間にか黒字倒産に陥ってしまうのも至極当然であることは確かです。
黒字倒産の回避方法

では、黒字倒産を回避するためにはどのような対策を取るべきなのでしょうか。
・常日頃から現金の流れを注視
現金不足は黒字倒産の大きな要因のひとつですから、やはり常日頃から現金の流れを徹底的に注視し、資金繰りに不安を抱えた際にはその都度、適切な対応をとれるようにしておくことが重要です。
具体的な方法としては、キャッシュフロー計算書や資金繰り表を正確に作成し、入念に手元資金の管理を行うこと。
「収益は十分にあるから」などと安心することなく、あくまでも事業継続の要となるものは現金であることを理解しておく必要があります。
・自由資本比率・自己資本比率・当座比率を正しく把握
キャッシュフロー計算書や資金繰り表の注視とともに、自由資本比率・自己資本比率・当座比率のそれぞれを正しく把握しておくことも大切です。
各比率は以下の計算式で求めることが可能です。
| 自由資本比率=(営業キャッシュフロー+投資キャッシュフロー)÷自己資本増加額×100 自己資本比率=純資産÷総資産×100 当座比率=当座資産÷流動資産×100 |
それぞれの説明については端折りますが、一般的に企業が正常に資金繰りを行うためには、自由資本比率が40%以上、自己資本比率が15%以上、当座比率が130%以上を維持するべきだとされています。
ですので、もしも各比率が上記の数値を下回っているようであれば、黒字倒産の危険性を孕んでいるということになりますが、裏を返せば、各比率の上昇に努めることによって黒字倒産の可能性を大きく軽減させることが可能となるわけです。
黒字倒産とは?のまとめ
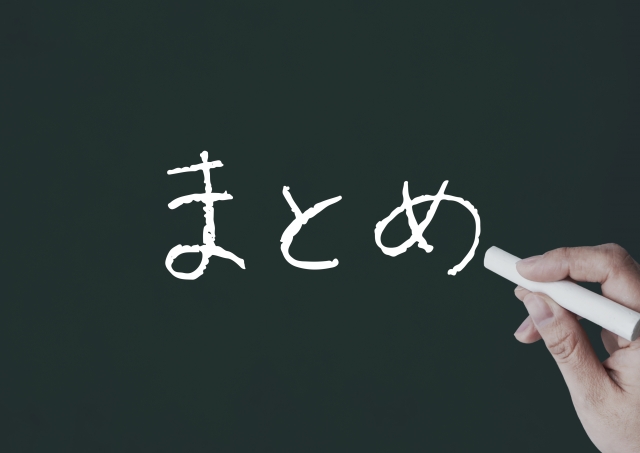
今回は黒字倒産と、その発生要因や回避方法についても解説しました。
黒字倒産とは、収入が支出を上回っているのにもかかわらず倒産してしまうことであり、大きな要因として挙げられるのは現金の不足です。
黒字倒産を回避するためにも、常日頃からキャッシュフロー計算書や資金繰り表の注視、さらには自由資本比率・自己資本比率・当座比率の正しい把握や手元資金、売掛金、買掛金のバランスを考慮に入れた資金管理を徹底して行っていくようにしましょう。














