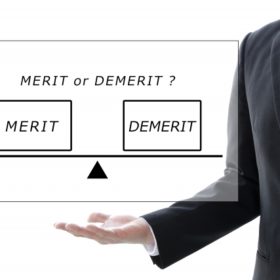資金ショートとは?~資金ショートの意味と、資金ショートにならない「資金繰り」について銀行員が解説
「よく『資金がショートする』と聞くけど、実際に経験したことが無いので意味が分からない。」
「資金がショートするってどういう状態なの?」
経営で気になるのは事業資金の確保です。
この記事にたどり着いたのは、資金ショートの意味を調べている人かも知れません。
資金ショートになると会社は大変です。
今、この記事を読んでいる人の多くはまだ経験者ではないので調べているのだと思います。
できれば経験して欲しくない資金ショートについて、その意味と防止策としての「資金繰り」のポイントを解説します。
私は銀行員として数多くの経営者に接し、事業資金の相談や資金繰りについてアドバイスをしてきました。
この記事は、実際に私が現場で経営者と話した「生の声」です。
また、これから起業を考えている人もいると思います。
そこで決算書などで使う用語は、説明も加えながらわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
資金ショートの意味とポイント
まずは資金ショートの意味と、資金ショートが発生する原因について解説するところからはじめましょう。
資金ショートとは?
資金ショートとは、手元の運転資金が足りなくなってしまうことです。
ショート(short)の直訳は「短い」以外に「不足」の意味もあります。
資金ショートと聞いて思い浮かぶのは、経営不振で資金が底をついた会社といったイメージでしょう。
確かにこれが資金ショートで最も多いケースですが、それ以外の原因でも資金ショートを起こすことがあるのです。
例えば経営自体は順調で利益も出ているのに、瞬間的に資金が不足する場合もあり、こうした状態を俗に「勘定合って銭足らず」と表現しますが、「黒字倒産」のほうが伝わりやすいかもしれません。
では、次項から具体的に資金ショートが発生する原因を解説します。
資金ショートが発生する原因
資金ショートが発生する原因の中で特徴的な3つを紹介します。
<資金ショートが発生する原因>
1.引き掛かり
2.未払い、クレーム
3.資金繰りの「読み違い」
原因1.「引き掛かり」~普通にあること
企業は売上(品物の販売や工事などサービスの供与)を回収し、仕入れ資金を支払い、残った利益を元手にまた仕入れして販売して……と繰り返していきます。
こういったサイクルを「運転資金の循環活動」と呼びますが、そのような難しい表現を使わなくても、要は「普通の経済活動」なのです。
しかしこのサイクルでも、売上が減少したり(売上増加が原因になることも)大量に仕入れをしたりすると、瞬間的にでも資金が不足してしまうことがあります。
こういった状態を「引き掛かり」と呼びますが、これは通常の企業経営ではよくあることで、銀行もネガティブにはとらえません。
原因2.未払い、クレーム~アクシデント
こちらは引き掛かりのように前向きな理由ではありません。
販売先に代金を請求しても回収できない(貸倒れ・相手先が倒産した場合など)ことがありますし、商品にクレームが起こり、代金が回収できなくなってしまうこともあります。
特に昨今は悪い情報ほど拡散するもので、不良品やクレームは起業にとって致命的なダメージになる恐れもあるのです。
原因3.資金繰りの「読み違い」~実は一番深刻
実はこれが一番深刻で、要は資金繰りを間違えてしまうことです。
最近は会計ソフトなどを導入する会社も増えていますが、入力するのもデータを分析して判断するのも最終的には人間です。
生きた人間だからミスもまたあり得るのですが、こと資金繰りに関しては間違いが許されませんので、ここは注意が必要です。
資金ショートを起こさない!~資金繰り改善に2つの「見直し」
資金繰りを改善するためのポイントは2つあります。
<資金繰りを改善する2つの「見直し」>
1.収入の見直し
2.支出の見直し
収入の見直し
収入の面では改善ポイントは絞られます。
企業における収入(売上)は販売する相手があってなり立つものなので、自社だけで劇的に改善するのは難しいからです。
手形、小切手
まず約束手形や小切手をもらっている場合は、これから将来的には廃止の方向なので、いまのうちから交渉して振り込みなどに変えるべきでしょう。
約束手形廃止など、取引適正化に向けた5つの取組公表:経産省 2022年2月15日
経済産業省が大企業と下請中小企業の取引適正化に向け「5つの取組」を公表している。2026年まで約束手形の利用を廃止することや、知財Gメンを創設し知財関連の対応を強化することなどで、同省は中小企業の賃上げ原資確保や、エネルギー価格・原材料価格上昇に対応するためにも取り組み強化が必要としている。
このほかの取り組みでは、3月にも価格交渉促進月間を実施し、下請中小企業振興法で規定された「助言(注意喚起)」を通して価格交渉の促進を図る。パートナーシップ構築宣言の大企業への拡大、実効性を向上させるために補助金によるインセンティブ拡充を検討する。商工会・商工会議所と下請かけこみ寺の連携で相談体制を強化する。
2月10日にオンラインで行われた「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」でも、萩生田光一経産相が「取引適正化に向けた5つの取組」を表明していた。
独立行政法人中小企業基盤整備機構/中小企業News/約束手形廃止など、取引適正化に向けた5つの取組公表:経産省
https://j-net21.smrj.go.jp/news/rh2rue0000002wwk.html
売掛金
売掛金の回収期間(回収サイトともいいます)は資金繰り改善の代表的な方法です。
売上が発生しても入金が3ヵ月後、つまり売掛金の回収期間が3ヵ月なら、決算上はその月に売上計上されたとしても、現金が手に入るのは3ヵ月後です。
このように売掛金が3千万円あるなら、販売先に3千万円の売上債権を保有している、端的にいえば3ヵ月無利息で3千万円を貸しているのと同じ意味なのです。
ですからここで、売掛金の期間をひと月短縮できれば、資金繰りは楽になります。
支出の見直し
支出の改善については、言うまでもなく「出ていくお金を減らす」ことが最優先課題で、その次は「どうしても出ていくお金は、ゆっくり払う」という2点になります。
固定費
固定費は、家賃や光熱費、そして人件費など売上の増減とは関係なく一定して必要な支出のことです。
固定費も、自分で見直す余地が見つからない場合は、税理士やコンサルティング関連の会社に相談してみるのもいいでしょう。
資金ショートとは?のまとめ
見直しで注意が必要なのは「商売には相手がいる」ということです。
仕入企業など力関係で優位に立っている場合などは、あまり強気に出過ぎると取引そのものにマイナスに影響してしまう恐れもあるからです。
また顧問税理士も、決算書を作るだけでは充分に仕事しているといえません。
経営改善に接触的に関与してくれる、もっと言えば「うるさいくらい口を出してくるご意見番」のほうが理想です。
そのようなプロなら、決算報告や融資の相談など銀行に同席してくれたり、支払い条件の交渉サポートをしてくれたりしてくれます。
税理士費用も少額ではありませんので、どうせお金を払うのなら「頼れるプロ」を探すべきです。
この記事が、皆さんの参考になれば幸いです。