事業を始めたり継続したりするにあたって、さまざまな資金が必要になります。
とくに設備資金は想定外の金額が必要になって、資金調達しなければならなくなることもあるでしょう。
設備資金が必要、しかし手元にお金がない場合には、どこかから融資を受ける必要があります。
設備資金の融資を行っているところはさまざまとあります。
どのようなところが貸し付けを行っているか、ここで詳しく見ていきましょう。
また設備資金として融資を受けるにあたって、押さえておくべきポイントが数多くあります。
このポイントについても解説しますので、設備資金の調達が必要になった際の参考にしてください。
目次
設備資金について理解しよう
まずは設備資金とはどのようなものかについてみていきます。
意外と設備資金について、正しく理解できていない経営者も少なくありません。
とくに運転資金との違いについてよくわかっていない人は多いため、しっかりと把握しておきましょう。
事業を維持・拡大するための資金
設備資金とは、会社が事業の維持や拡大するために設備投資をする際に、必要な資金を指します。
設備資金の中には、さまざまな用途があります。
工場の建設や増設、機械設備を購入するための生産能力増強が挙げられるでしょう。
また設備の老朽化対策のための生産能力維持、エコの時代で求められる環境対応が該当します。
そのほかに新事業に進出するための資金や、社宅などの建設をはじめとした福利厚生施設を作るための資金も、設備資金に該当します。
設備資金というと、工場や機械装置の購入などの利益を生み出すための、投資というイメージをもっている人もいるでしょう。
しかし実際には福利厚生施設の建設など、利益を生み出さないものも設備投資に当てはまります。
設備投資するためには、まとまったお金が必要です。
大企業のような経営基盤が強固なところであれば、自己資金でねん出できるかもしれません。
しかし中小企業だと、なかなか自己資金だけでまかなうのは厳しいでしょう。
この場合ほかのところから、融資を受ける必要が出てくるわけです。
運転資金との違い
法人の代表者の中でも、運転資金と混同している人は少なくありません。
しかし両者には違いがあります。
両者の相違点は、継続的に必要なお金かどうかです。
設備資金は設備や施設などの、事業に必要なものを購入するための一時的な資金をいいます。
一方運転資金とは、事業を継続するために必要な継続的に発生する資金のことです。
テナントの契約に必要になる保証金や敷金、備品の購入などは設備資金に該当します。
一方人件費や公共料金などは、運転資金になります。
テナントの保証金や資金などの初期費用は、設備資金です。
一方テナントの賃料は毎月発生する資金なので、運転資金に分類されます。
資金調達する際には設備資金と運転資金、どちらに該当する資金なのか十分に検討してください。
設備資金のほうが運転資金よりも返済期間は長め
設備資金と運転資金の違いとして、返済期間の長さも挙げられます。
一般的な傾向として、設備資金のほうが運転資金よりも返済期間を長めにされがちです。
設備資金の場合、建物の建設や設備の導入など多額の借り入れになることが多いからです。
融資金額が大きくなるので、返済期間も余裕をもって長めに設定されます。
別項で詳しく見ていきますが、日本政策金融公庫という政府系金融機関では、設備資金と運転資金の融資の両面を行っているものです。
該当する商品は一般貸付なのですが、運転資金は最長7年の返済期間であるのに対し、設備資金は10年までとなっています。
設備資金で借り入れれば、余裕をもった返済計画を立てられるわけです。
設備資金の融資方法
設備資金が必要、しかし手持ち資金だけではすべてを賄えないというのであれば、どこかから借り入れないといけません。
設備資金を融資している金融機関は、数多くとあります。
その中でも主な資金調達方法として、以下のようなアプローチが考えられます。
1. 日本政策金融公庫
2. 中小機構
3. 民間の金融機関
それぞれどのような条件で貸し付けを行っているのかについて、詳しく見ていきましょう。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫では「設備資金貸付利率特例制度」と、呼ばれるものを用意しています。
設備資金貸付利率特例制度は、国民生活事業と中小企業事業のふたつに分類されます。
国民生活事業の場合一般貸付もしくは特別貸付、マル経融資・生活衛生貸付のいずれかの融資を受け設備投資を行う場合です。
なおかつ向こう5年間で、付加価値が2%以上の伸び率の見込みのある投資であることが条件です。
一方中小企業事業の場合、5年間で付加価値の伸び率2%以上が期待される設備資金目的で、融資を受ける法人が対象となります。
しかしこちらは特別貸付制度のみが該当になりますので、注意しましょう。
国民生活事業・中小企業事業ともに、対象の制度であっても用途によっては一部利用できない制度もあります。
手続きをする前に確認しておきましょう。
こちらの制度を利用すると、従来の利率よりも優遇措置が取られます。
いずれの事業でも、融資から2年間は各融資制度で定められている利率から、0.5%優遇されます。
ただし優遇した結果、利率が0.3%未満になるようなら0.3%が適用されるので注意しましょう。
中小機構
中小機構とは正式名称を「中小企業基盤整備機構」といいます。
独立行政法人で、中小企業関連の政策の実行機関です。
中小企業の成長をステージに応じて、サポートしている機構でもあります。
中小企業の事業をサポートするために、各種融資を用意しています。
設備投資のための資金調達をする際には、設備投資向け融資を利用しましょう。
高度化事業と呼ばれており、都道府県と連携して診断助言や貸し付けを行っています。
高度化事業にはいくつか特徴があります。
まず政策性を重視した融資制度になっていることです。
組合などが集団化や共同化するための事業や第三セクターなど、中小企業を支援する事業などが対象の融資制度になっています。
借入するにあたって、金利は気になるところでしょう。
利率によって、返済負担が左右されるからです。
設備資金はまとまった資金の借り入れがメインとなるので、少しでも金利の低いところで借入したいところです。
高度化事業では低利、しかも固定利率が適用されます。
特定の事業に該当する場合には、無利子になることもあるほど優遇されています。
都道府県が窓口になっているのも、特徴のひとつです。
ただ貸付を行うのではなく、コンサルティングがあわせて実施されるのも、他の融資制度にはない特徴です。
申し込む際には事業計画などを策定する必要があります。
しかし専門家が各法人の状況に即した、適切なアドバイスをしてくれます。
そのため過大な投資などを回避でき、スムーズな事業運営が可能になるでしょう。
税制面の優遇措置が受けられる可能性もあります。
人口30万人以上の市で、高度化事業に基づく工場や倉庫・店舗を取得した場合、そこで行った事業に課せられる事業所税は非課税です。
中小機構の貸付条件は事業に必要な土地や建物、設備の購入資金で資産計上できるものが対象です。
融資金額はうえで紹介したものを取得するために、必要な額の80%が上限となります。
ただし中小企業の振興に係る関係法律の認定が受けられた場合には、90%が上限となります。
気になる金利は、令和4年度に決定したものに関しては0.4%です。
中小企業の振興に係る関係法律の認定を受けた事業の場合には、無利子です。
さらにこの利率は返済期間常に固定となります。
金利は毎年設定が見直されるため、最新情報は中小機構のホームページなどで確認してください。
貸付期間は最長20年です。
またうち3年を上限として据置期間も設定されます。
民間の金融機関
法人が資金調達するにあたって、銀行融資を真っ先に連想する人もいるでしょう。
民間の金融機関でも、設備資金に関する融資を行っています。
メガバンクなどの都市銀行のほかにも、地方銀行や信用組合などでも対応しているところは多いのです。
ネットバンクでも設備投資に対する貸し付けを、積極的に行っているところも少なくありません。
また一部金融機関では「設備資金貸付」などの名称で、融資を行っていない場合もあります。
商品名が異なっても、設備資金に回せるようなローンを販売している可能性がありますので、問い合わせてみましょう。
設備資金の融資に関しては、金融機関ごとで条件は異なります。
たとえば返済期間ですが、設備資金の場合10年を上限としているところもあれば、20年以内としているところも見られます。
また同じ設備資金の融資であっても、申込者によって案内が変わってくる場合もあるのです。
この点にも注意して、用途と必要な金額を明確にして担当者に説明を行いましょう。
設備資金借入するにあたっての必要書類
ほかの融資同様、設備資金の借り入れにあたっては審査が実施されます。
この審査を受けるために、いくつか必要書類を用意して提出しなければなりません。
金融機関によって一部内容が異なる可能性はあるものの、一般的に以下のような資料を提出するように求められます。
1. 決算書
2. 見積書
3. 事業計画書
4. 資金繰り表
どのような書類を準備しなければならないのか、以下で詳しく紹介しましょう。
決算書
まずは決算書は必須と思っておいた方がよいでしょう。
法人の経営成績や財務状態などを、把握するための貴重な資料になるからです。
決算書とは、財務諸表のことを指すと考えてください。
財務諸表とは貸借対照表と損益計算書・キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書のセットになったものです。
一般的に直近2期分の決算書の提出を求められると思って、あらかじめ資料を用意しておきましょう。
中には個人事業主で、設備投資するための資金が必要で借り入れたいと思っている人もいるでしょう。
個人事業主対象で、設備資金を融資している金融機関も少なくありません。
もし個人事業主が申し込む際には決算書の代わりに、確定申告書を提出する形になります。
確定申告書の内容から、利益率や資産額を確認して融資の可否を判断する形です。
見積書
見積書は購入しようと思っている設備や、不動産の金額について記載されているものです。
設備や不動産を販売しているお店にお願いして、あらかじめ見積書を作成してもらいましょう。
見積書の内容をベースにして、借入金額が妥当なのか確認します。
事業計画書
事業計画書は今後の事業の目標や目的と達成するために、どう事業運営していくかを説明するための書類です。
今後どのような方向性で事業を進め、どう利益を確保していくかを中心に説明していくとよいでしょう。
設備投資の場合、まず設備投資の種類を明確にしておく必要があります。
新製品開発や新規分野開拓などの能力増強投資、人件費削減のための合理化投資などがあるでしょう。
さらに老朽設備への対策などの更新投資・福利厚生や環境対策などの非生産型投資など、どのための資金調達なのかを明記していきましょう。
またその設備投資が、なぜいま必要なのかについて記載しておきます。
ただの法人代表者の思い付きではないか、企業の中長期ビジョンと合致しているかなどを説明しておくべきです。
そのうえで設備投資が妥当であるかについての記述も、言及するとよいでしょう。
このように総合的に設備投資に関する説明をすることで、銀行の担当者の納得を得やすくなります。
資金繰り表
資金繰り表も必須書類のひとつになります。
法人や個人の収入や支出を表にして作成しましょう。
資金繰り表には主に2種類あります。
資金繰り実績といって、これまでの実績をベースに作成したものがまずひとつ目です。
もうひとつが資金繰り予定表と呼ばれる、これからの資金繰りの予想に関する書類になります。
設備投資用の資金の融資を受けても、きちんと返済できることを立証するような書類づくりを目指しましょう。
ただし非現実的な見込みでは、当然審査も厳しくなります。
実情に合わせた資金繰り表を作成してください。
設備資金融資に関する審査のポイント
金融機関は設備投資用の資金融資の申し込みがあれば、ほかのローン同様審査が実施されます。
審査基準などは各金融機関で、基準は公開していません。
しかし一般的に以下で紹介する3つのポイントを中心に、考査されるといわれています。
1. 資金調達の妥当性
2. 返済能力の有無
3. 担保の資産価値
それぞれどのような部分がチェックされるのかについて、以下でまとめました。
資金調達の妥当性
設備資金の計画を見て、妥当なものかどうかは審査の中で考慮される項目です。
具体的には4つのポイントを重視されると思ってください。
まずは自己資金と外部からの調達の割合です。
設備投資に必要な資金の中で、どのくらいが自己資金で占めるのかはチェックされます。
自己資金の割合が大きければ大きいほど、融資実行される可能性は高まります。
ふたつ目は運転資金が、どの程度増えるかに関することです。
設備を導入すれば、おのずと運転資金も増えていきます。
運転資金の増加分をしっかり負担できるのかも、しっかりチェックします。
3つ目は資金調達の方法です。
借入なのかリースなのかによって、銀行の心証も変わっていきます。
最後に資金調達先が複数あった場合、どの分担割合かについても考査されるでしょう。
返済能力の有無
お金を借りる以上、後日返済しなければなりません。
金融機関としては貸したお金が返済されないと、不良債権を抱えてしまって損害を被ってしまいます。
そこで十分な返済能力があるかどうかは、審査するにあたって欠かせない項目です。
設備投資対象の案件だけでなく、法人全体の事業収支を試算し、返済能力の有無を確認します。
経常利益や減価償却・引当金、増加する運転資金から税金や役員の賞与などを差し引いて、返済金を算出します。
少なくとも今回の設備投資に関する案件単体で、返済能力があるかどうかをベースに、審査の可否を判断する形です。
担保の資産価値
もし法人やその代表者が何らかの資産を有している場合、それを担保として差し出せます。
この場合担保の価値も判断したうえで、融資可能かどうか判断します。
担保として差し出せるものとして、多くの人は不動産を連想するでしょう。
しかし不動産のほかにも機械や車両などの動産も、担保として差し出せます。
そのほかにも有価証券や売掛債権も、担保にできます。
担保があれば、いざ債権回収できなければ担保を押さえればよいわけで、融資する側もリスクマネジメントがやりやすくなるのです。
そのため審査の中でも、ポジティブな影響を与える可能性が高いでしょう。
設備資金融資の申し込みの際の注意点
設備資金の借り入れを検討している法人の代表者がいれば、注意しなければならないポイントがあります。
以下の点については、とくに注意しておきましょう。
1. 不動産購入時には担保の差出が必要
2. プライベート用の車両は設備にあらず
3. 運転資金に流用するのは違反行為
それぞれどのようなことに注意しなければならないか解説しますので、参考にしてください。
不動産購入時には担保の差出が必要
不動産購入のための融資を願い出ることは、もちろん可能です。
しかし対象の物件を担保にすることが、前提条件になると思ってください。
一部無担保・無保証人で、申し込みできる商品もあります。
しかし不動産購入するための融資であれば、その物件は担保にするよう担当者から求められるものだと考えましょう。
プライベート用の車両は設備にあらず
設備資金として、法人で使用する車両購入も含まれます。
しかしこれは営業用の車両や運送用のトラック、クレーン車などの作業車などが対象です。
一方プライベートで使用するための乗用車は、設備資金としては認められません。
また事業用車両を購入するための資金融資を申し込むためには、見積書が必要です。
もし購入する車両が見つかったら、速やかに販売店のスタッフにお願いして、見積書を作成してもらいましょう。
運転資金に流用するのは違反行為
設備資金として借り入れたお金を運転資金など別の目的で使用した場合、資金使途違反に該当します。
設備資金として借り入れたお金の一部が余ったので、運転資金に回すなどはできません。
もし別の用途で借り入れたお金を使ってしまった場合、何らかのペナルティを受けることになるかもしれません。
たとえば借金の速やかな返還、今後融資が受けられなくなるなどの罰則が考えられます。
また融資実行後、金融機関が確かに当初の目的通りにお金が使われているか、領収書を提出するように求められる場合もあります。
設備投資のためにお金を使った場合、先方に領収書を発行してもらって、なくさずしっかり保管してください。
ビジネスローン審査で通りやすいおすすめな会社比較表で解決
法人や個人事業主が資金調達を検討する際、即日融資が可能な自社はいくつかあります。ビジネスローン審査で通りやすいおすすめな会社には、審査基準が比較的「ゆるい」自社も存在します。それぞれの自社には特徴がありますが、ここでは審査が比較的甘く即日融資が可能な法人融資会社をご紹介します。
| 業者名 | 融資対象 | 金利 | 入金スピード | 融資限度額 |
|---|---|---|---|---|
| アクトウィル | 法人 | 7.5%~15% | 最短即日 | 最大1億円 |
| AGビジネスサポート | 法人・個人事業主 | 3.1%~18% | 最短即日 | 1000万円 |
| ファンドワン | 法人 | 2.5%~18% | 最短即日 | 1億円 |
| デイリーキャッシング | 法人・個人 | 5.2%~18% | 最短即日 | 8000万円 |
| 株式会社オージェイ | 法人・個人 | 9.5%~18% | 最短即日 | 1億円 |
| Carent | 法人 | 7.8%~15% | 最短即日 | 500万円 |
| オリックス・クレジット | 法人・個人 | 6.0%〜17.8% | 最短即日 | 500万円 |
| ビジネスパートナー | 法人・個人 | 9.98%〜18.0% | 最短5日 | 500万円 |
| いつも | 法人・個人 | 4.8%~18.0% | 最短即日 | 500万円 |
| プロミス | 個人 | 6.3%~17.8% | 最短即日 | 300万円 |
おすすめのビジネスローン会社概要
アクト・ウィル

アクトウィル株式会社は、法人向けの事業者金融です。申込は電話かメールでメールだと24時間受付しています。
必要書類はFAXで提出でき、最短即日で審査可能です。アクト・ウィルは低金利と大口融資が可能で、実質年率7.5%~15%と比較的低い金利で融資が受けられます。また、最大1億円の融資が受けられるため、まとまった資金の調達をしたい企業におすすめです。融資は法人契約の為ため、代表者の連帯保証のみで第三者による保証人や不動産担保は不要です。メールでの相談やお問い合わせは24時間受付してますので、営業時間外でも問い合わせられます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 7.5%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | アクトウィル株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31521号 |
| 住所 | 〒160-0022 東京都豊島区東池袋3-11-9 |
| 電話番号 | 03-5944-9168 |
| FAX番号 | 03-5944-9169 |
| 営業時間 | 平日9:00~20:00 |
AGビジネスサポート

AGビジネスサポートは、企業の成長を支援するためのビジネスローンを提供しています。AGビジネスサポートのビジネスローンは、資金調達のニーズに応じて柔軟に対応し、迅速な審査と融資を実現します。特に、中小企業やスタートアップ企業にとって、資金繰りは重要な課題です。AGビジネスサポートでは、経営者の皆様が抱える資金の悩みを解消し、事業の発展をサポートすることを使命としています。
AGビジネスサポートのビジネスローンは、用途に応じた多様なプランを用意しており、設備投資や運転資金、さらには新規事業の立ち上げ資金など、さまざまなニーズに対応可能です。審査基準も柔軟で、過去の実績や信用情報だけでなく、将来のビジョンや事業計画を重視した評価を行います。これにより、資金調達が難しいとされる企業でも、安心してご相談いただけます。さらに、AGビジネスサポートでは、専門のスタッフが個別にサポートを行い、最適なプランをご提案します。お客様のビジネスの特性や成長段階に応じたアドバイスを行い、資金調達のプロセスをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1000万円 |
| 金利 | 3.1%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | AGビジネスサポート株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01262号 日本貸金業協会会員第001208号 |
| 住所 | 東京都港区芝2丁目31-19 |
| 電話番号 | 0120-027-120 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 平日9:30~18:00 |
ファンドワン

ファンドワン株式会社は、東京都豊島区南大塚に本社を構える、事業者向け金融サービスを提供する企業です。2020年1月に設立され、資本金5,000万円を基盤に事業を展開しています。同社は、全国の事業主に対し、迅速かつ柔軟な与信判断と安心の金利帯で資金調達を支援しています。
提供するサービスには、無担保の事業者ローンや、不動産・売掛債権を担保としたローン、車担保融資、介護・診療報酬担保融資など、多様な商品が含まれています。最短40分のスピード審査や、最大1億円の大型融資が可能である点が特長で、赤字決算や税金・社会保険料に課題を抱える事業主にも柔軟に対応しています。
ファンドワン株式会社は、単なる資金提供に留まらず、中小企業の成長を支援し、地域社会や日本経済全体の活性化に貢献することを使命としています。これまで、経営難に直面した多くの企業の資金繰りや経営再建をサポートしてきました。同社は、経験豊富なスタッフが最適なプランを提案し、事業主とともに成長を目指すパートナーとして信頼されています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 2.5%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | ファンドワン株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(2)第31816号 |
| 住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚二丁目39-11 ヒサビル6階 |
| 電話番号 | 03-5395-8888 |
| FAX番号 | 03-5395-8800 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
デイリーキャッシング

株式会社デイリープランニングは、個人のお客様から法人のお客様まで幅広いニーズに対応したローンサービスを提供している企業です。主に「フリーローン」「おまとめローン」「不動産担保ローン」「ビジネスローン」を取り扱い、それぞれの状況に最適な融資プランを提案しています。
同社のサービスは、全国どこからでも利用可能で、急な資金需要に柔軟に対応します。特に、急な出費や資金繰りの困難を抱える方々に、迅速かつ確実な融資の手続きを提供し、お客様の生活やビジネスを支えています。
さらに、デイリープランニングでは、融資の申し込みが簡単で、インターネットや電話、店舗での手続きもスムーズ。お客様一人ひとりの状況に合わせた親身な対応を心掛け、信頼性の高いサービスを提供しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 8000万円 |
| 金利 | 5.2%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社デイリープランニング |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(3)第31698号 |
| 住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-12徳永ビル4階401号 |
| 電話番号 | 03-6284-3674 |
| FAX番号 | 03-6284-3675 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
株式会社オージェイ

株式会社オージェイは、法人向けに多彩な融資サービスを提供する企業で、事業資金の調達をサポートします。提供する融資メニューには、無担保融資、手形割引融資、不動産担保融資、動産担保融資、ファクタリング、診療報酬担保融資などがあり、さまざまな事業ニーズに柔軟に対応しています。
同社は、急な資金調達が求められる場面でも迅速に対応できる体制を整えており、審査もスピーディで信頼性の高いサービスを提供しています。また、日本貸金業協会に加盟しており、法的にも安心して利用できることが保障されています。中小企業や個人事業主など、資金繰りに困っている事業者に対して、親身なサポートを行い、ビジネスの安定と成長を支援しています
さらに、オンラインで簡単に申し込めるため、全国どこからでも迅速で効率的な資金調達が可能です。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 9.5%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社オージェイ |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31549号 |
| 住所 | 東京都中野区中央1-32-5 青光堂ビル3F |
| 電話番号 | 03-5332-3833 |
| FAX番号 | 03-5322-3834 |
| 営業時間 | 平日10:00~15:00 |
Carent

事業資金のニーズに柔軟に応える「Carent ビジネスローン」は、スピーディーで安心の融資サービスです。中小企業や個人事業主の方々が直面する資金繰りの課題を解決し、成長をサポートします。
柔軟な条件設定:事業規模や状況に合わせた融資プランをご提案。迅速な審査:最短○日で審査完了、資金調達をスムーズに。安心のサポート体制:専門スタッフがご相談から契約まで親身に対応します。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 7.8%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社IPGファイナンシャルソリューションズ(キャレント) |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(5) 第31399号 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-24-4 WEST HILLビル5階 |
| 電話番号 | 03-5740-5087 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 |
オリックス・クレジット

オリックス・クレジット株式会社は、1979年にオリックス株式会社とフランスの大手信販会社セテレム社の合弁により設立され、オリックスグループ初の個人向け金融サービスを提供する企業として誕生しました。設立当初はショッピングクレジットや有担保ローンを中心に展開していましたが、1987年には低金利かつ高額融資が可能な「VIPローンカード」を発売し、プレミアム・カードローン市場の先駆者としての地位を築きました。
その後、貸金業法の改正に伴い、市場環境の変化に対応するため、これまで培った与信やオペレーションのノウハウを活かし、金融機関向けの信用保証事業に注力。現在では全国250社以上の金融機関と提携し、同社の主力事業の一つとなっています。
さらに、オリックス株式会社から事業を継承し、モーゲージバンク事業にも参入。「フラット35」を中心とした住宅ローン商品を提供し、新築だけでなく中古物件のリノベーション向けや地域活性化と連携した商品など、多様なニーズに応じたサービスを展開しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 6.0%〜17.8% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00170号 |
| 住所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー |
| 電話番号 | 非公開 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
ビジネスパートナー
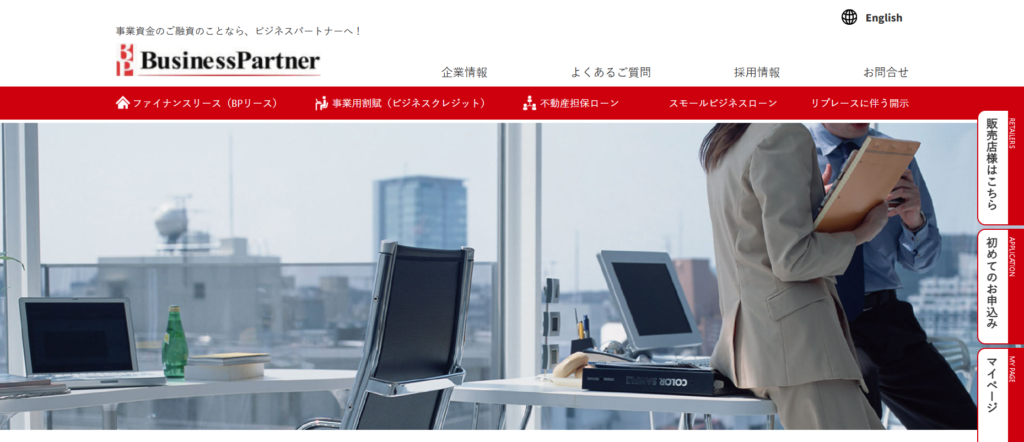
株式会社ビジネスパートナーは、1999年に設立され、東京都新宿区に本社を構える金融サービス企業です。中小企業や個人事業主向けに、柔軟な事業資金融資を提供しており、特にスピーディーな資金調達を求める事業者に支持されています。
同社の主力商品である「スモールビジネスローン」は、来店不要で契約可能な無担保ローンで、事業資金の用途に応じた自由な活用が可能です。原則として担保や保証人を必要とせず、手数料もかからないため、資金調達のハードルが低いのが特長です。また、セブン銀行ATMを活用することで、365日24時間、資金の引き出しや返済が可能な利便性の高いサービスを提供しています。
さらに、ファイナンスリース「BPリース」や事業用割賦「ビジネスクレジット」、不動産担保ローンなど、多様な資金調達の選択肢を用意。事業運営に必要な資金を柔軟に確保できるよう支援し、企業の成長をサポートしています。特に、事務処理の簡素化や全額損金処理の可能性など、経営効率を向上させるメリットも提供しています。
ビジネスパートナーは、迅速かつ柔軟な資金提供を通じて、中小企業の発展を支える信頼できる金融パートナーとして、多くの事業者に利用されています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 9.98%〜18.0% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短5日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社ビジネスパートナー |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01500号 |
| 住所 | 〒160−0022 東京都新宿区新宿6‐27−56 新宿スクエア6F |
| 電話番号 | 非公開 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
いつも
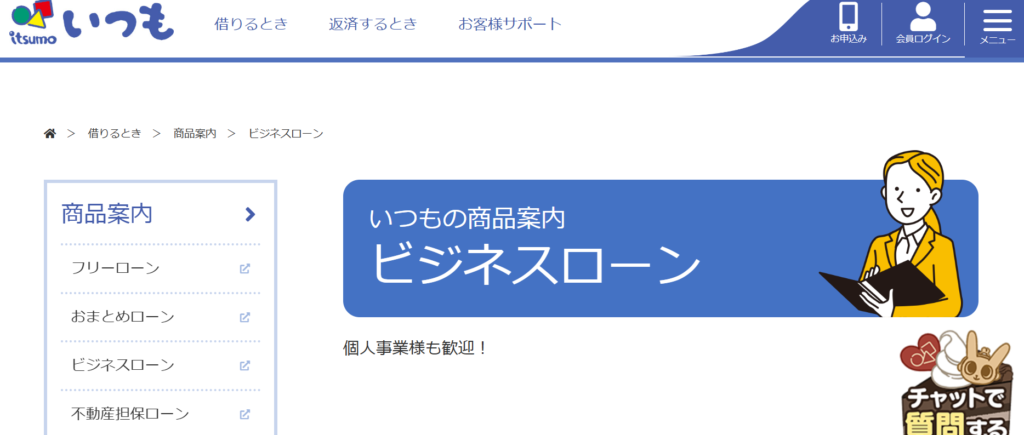
株式会社K・ライズホールディングス(ブランド名:いつも -itsumo-) は、個人および法人向けに多様なローンサービスを提供する金融会社です。主な取り扱い商品には、フリーローン、おまとめローン、ビジネスローン、不動産担保ローンなどがあります。
特に ビジネスローン は、個人事業主や法人の事業資金ニーズに対応し、迅速かつ柔軟な融資を実施。オンラインでの申し込みは 24時間365日対応可能 で、最短30分での審査・融資も可能です。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 4.8%~18.0% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社K・ライズホールディングス |
|---|---|
| 登録番号 | 高知県知事(4)第01519号 日本貸金業協会会員 第005847号 |
| 住所 | 高知県高知市杉井流5-18 |
| 電話番号 | 0570-055-126 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 不明 |
プロミス

個人事業主の資金調達をサポート!プロミス「自営者カードローン」は事業を運営する上で、急な資金ニーズ に対応できる柔軟なローンがあると心強いものです。プロミスの「自営者カードローン」は、個人事業主の方を対象 としたローンサービスで、最大300万円 まで借入可能。事業資金だけでなく、プライベートな用途 にも利用できるため、事業と個人の資金管理をスムーズに行えます。
申し込みは 24時間365日 受け付けており、インターネットから簡単に手続き可能。さらに、スピーディーな審査と融資 により、急な資金調達にも対応できるのが大きな魅力です。例えば、運転資金や設備投資、仕入れ資金 など、さまざまな用途で活用できます。また、必要書類も本人確認書類 と 事業内容を確認できる書類(例:確定申告書) のみとシンプル。手続きが簡単で、事業を営む方の負担を最小限に抑えられます。。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 300万円 |
| 金利 | 6.3%~17.8% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00615号 |
| 住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル |
| 電話番号 | (03)6887-1515 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
設備資金融資に関するまとめ
設備資金の融資に対応しているところは、さまざまなものがあります。
日本政策金融公庫や中小機構、全国にある民間の金融機関が対応しているものです。
とくに創業時には、設備投資が必要になるケースが多く、融資だけでなく各種補助金制度をあわせて活用することで、自己資金の負担を軽減できる可能性があります。
設備資金を調達するにあたって、注意すべきポイントもあります。
とくに設備資金のための借入金であり、ほかの用途にお金を回せない点には注意してください。
あとでほかのためにお金を使ったことが発覚すると、何らかのペナルティを受けないといけません。















