事業者にとって、常に頭の中に入れておかなければならないのは資金繰りの問題です。
ビジネスをしていると原材料費の支払いや人件費など、出ていくお金は日々発生します。
いざ支払日になっても手元に現金がなければ、支払いができません。
支払日を守れなければ、会社の信用力低下につながります。
取引停止などが起こり、経営が立ち行かなくなり、最悪倒産するケースも出てきます。
そこで手持ち資金が足りなくなった時にどう資金調達するかは、事業者にとって大きな課題です。
ここでは事業性資金の借入方法について紹介しますので、いざというときの参考にしてください。
目次
資金繰りの必要性を理解しよう
事業者の「黒字倒産」という言葉を聞いたことはありますか?
通常黒字経営ができていれば、資金繰りに窮することはないと思われがちです。
しかし帳簿的には売り上げ好調にもかかわらず、支払日が迫っていても必要な資金が確保できない会社は結構あります。
帳簿上は利益が出ていても…
帳簿的にはきちんと収益が出ていても、それはあくまでも会計上の話です。
事業者の帳簿の数字はプラスでも、リアルタイムの現金の出入りとは無関係です。
帳簿の数字と実際の現金の動きにはタイムラグが生じます。
皆さん売掛金を持っていませんか?
事業者は売上が発生した当日、実際にお金が入ってくるわけではありません。
売上が発生した後で、一定期間の売上金を後日回収する形をとっている法人は多いでしょう。
これを売掛金といいます。
ただし売掛金が回収できていない間でも経費や仕入れに関する費用など、出ていくお金は発生します。
もし手持ち資金がなければ、帳簿上は利益が出ていても支払いがままならなくなり、最悪倒産することもあり得ます。
このため黒字倒産がしばしば発生してしまうわけです。
資金繰り予定表を作成しよう
上で紹介した事業者の黒字倒産を避けるためにおすすめなのが、資金繰り予定表を作成することです。
資金繰り予定表とは、現金の動きや取引内容をまとめたものです。
資金繰り予定表を見れば、将来どの程度のお金の出入りが発生するのか、その間現金がどのくらい不足するのかがわかります。
あらかじめ「このタイミングで現金が不足する」ことがわかっていれば、対策もしっかり講じられます。
不足分のお金をどこかから借入して賄うといった対策も可能です。
借り入れることは決して悪くない
一般的に借金といわれると、あまり良いイメージがないかもしれません。
しかし健全な経営を続けるために、借入で資金調達するのは決して悪くありません。
借入で資金確保することによって、よりスピーディに事業を進められます。
たとえば新規事業を手掛けようと思って、事業立ち上げに1億円必要だったとします。
しかし手持ち資金が7,000万円しかなければ、このままでは新規事業をすぐには進められません。
しかし、たとえば3,000万円をどこかから借り入れられれば、必要な金額1億円を確保できるのですぐに事業を開始できます。
事業がうまくいくかどうかは、タイミングも重要な要素です。
不足分を借り入れることで、このタイミングをみすみす逃すこともなくなります。
事業を運営するにあたって、リスクは常に存在します。
しかも予期しない不可抗力によって、事業が立ち行かなくなることも十分想定できます。
記憶に新しいのは、いわゆるコロナ禍です。
コロナ禍によって、自粛生活が広く浸透し、飲食店はじめ小売業者は深刻な影響を受けました。
このように自分たちではどうしようもないことで、経営が行き詰まることもありうるわけです。
売上が何かしらの問題で激減して、それでも支払いを進めなければいけなくなると資金繰りがショートしてしまいます。
このような突発的な事態に対処するために、借入を進めるのは法人を守るためにも時として必要になるわけです。
事業性資金を借り入れるにはどうすればいい?主な借入方法を解説
事業を運営していると、時としてどこかからお金を借りることも必要になるでしょう。
事業者が利用できる借入方法はいくつかあります。
主な方法として、以下のような手法が考えられます。
1.日本政策金融公庫
2.プロパー融資
3.信用保証貸付
4.ビジネスローン
5.自治体
それぞれに異なる特徴があり、メリットデメリットの2面性があります。
その時々の状況でより良い方法で資金調達を進めましょう。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は政府系の金融機関です。
日本政策金融公庫では、事業者向けの融資をいろいろと実施しています。
日本政策金融公庫の特徴として、見逃せないのは低金利で借入できるところです。
どの制度で借り入れるかもしくは借入のタイミングで、金利は若干異なります。
しかしおおむね担保不要であれば2%台、担保を用意できるのであれば1%台での借入も可能です。
また起業のための資金融資を行っているのもおすすめのポイントです。
以下で紹介する銀行からの融資の場合、2期以上の業歴があるなど、ある程度法人としての実績を有していることが融資の条件としているところも少なくありません。
これから起業する人に対して銀行は融資を渋る傾向がある半面、日本政策金融公庫は比較的積極的に融資しています。
ただし融資実行されるまでにある程度時間がかかるので、注意が必要です。
申し込んでから面談を受けて、審査を進めるのでどんなに早くても融資実行されるのは1カ月くらい後です。
資金繰りが切迫しているのなら、日本政策金融公庫から融資を受けるまでをどう凌ぐかも併せて考えなければいけません。
プロパー融資
事業者の借入方法として、「銀行融資」を真っ先に連想する人も多いでしょう。
よく言われる銀行融資とは、このプロパー融資を指すと思ってください。
プロパー融資とは、金融機関が直接借入希望者を審査して融資の可否を判断する方法です。
融資基準は、金融機関ごとでそれぞれに有しているので、融資額や金利などの条件も異なります。
プロパー融資の特色として、大型融資に対応している点は見逃せません。
あくまでも法人の信用力次第ですが、十分な信用があると判断されれば数億円規模の借入も可能です。
設備投資などは機械や敷地の購入などまとまった資金が必要になりがちなので、プロパー融資を利用するといいでしょう。
またプロパー融資を受けることができれば、法人の信用力向上につなげられます。
銀行の審査は一般的に厳しいといわれているからです。
プロパー融資を受けられるのは銀行から十分な信用を得られていることになります。
銀行のお墨付きを受けていれば、安心してビジネスを進められるでしょう。
プロパー融資の場合、審査が厳しいので申し込んでも希望する額を調達できるかどうかはわかりません。
銀行自身が判断して融資するので、もし債権が焦げ付いた場合その損害をもろに被らなければいけなくなります。
自分たちのリスクマネジメントとして、審査を厳格にして融資先を厳選する傾向が見られます。
信用保証貸付
事業者向けの信用保証貸付も銀行融資の一種の手法です。
信用保証協会というところが保証を付ける条件の下で、金融機関がお金を貸し出す方法です。
信用保証協会が保証してくれるので、銀行としてみれば融資しても不良債権化するリスクが低くなるので貸しやすくなります。
ですから業歴が多少浅かったり、経営状況が好調でなかったりする会社でも借り入れやすくなるわけです。
たとえ債務者の法人が返済不能の状態になっても、信用保証協会が代わって立て替えてくれます。
このため審査がプロパー融資よりも甘くなるだけでなく、金利が低くなるなど借入の条件も有利になるかもしれません。
ただし信用保証協会が保証するにあたって、保証料を支払わなければいけないので注意が必要です。
また銀行だけでなく、信用保証協会でも審査を行うので融資実行されるまでに時間がかかります。
場合によっては融資実行されるまでに、資金ショートしてしまうことも考えられます。
ビジネスローン
事業者向けのビジネスローンとは、事業性資金に特化した金融商品です。
ビジネスローンは銀行のほかにも、消費者金融をはじめノンバンクでも取り扱っている商品です。
ビジネスローンのおすすめポイントは、短期間で融資実行してくれるところです。
どんなにかかっても1週間から10日後には融資実行してくれるでしょう。
一部ノンバンクの中には、最短即日融資しているところもあります。
当初予定されていた売掛金が先方の事情で回収できなくなった、急な出費が発生して急激に資金繰りが悪化したときなどには重宝します。
またノンバンクなど貸金業者の場合、総量規制に基づき融資を行わなければいけないルールがあります。
総量規制とはその人の年収の1/3を超えて貸付できないというものです。
しかしビジネスローンはノンバンクでも総量規制の対象外ですから、年収の1/3を超える融資が受けられます。
ビジネスローンの審査は甘めですが、金利が高めになる点に注意しましょう。
銀行で3〜14%、ノンバンクだと5〜18%が相場といわれています。
もしビジネスローンを利用するなら、入金があれば優先的に返済資金に充てましょう。
そうして借入期間を短くして、利息の支払いをできるだけ圧縮することが大事です。
またビジネスローンは、大型融資には対応していません。
ノンバンクの場合300〜500万円、銀行でも1,000万円を上限としている商品が多いです。
運転資金やつなぎ融資など、小口の借入の際に利用を検討するといいでしょう。
自治体
地方自治体の中には、主に経営基盤がぜい弱な中小企業・事業者向けの制度融資を行っている場合があります。
自治体と地元の金融機関や信用協会とが連携して、法人にお金を貸し付ける制度です。
自治体融資の場合、借り入れ条件の良いものが多いです。
民間の場合、収益目的で貸し付ける側面が強いです。
一方自治体の融資の場合、中小企業のサポートを目的としているので借り入れやすい条件で融資を行っています。
金利も3%前後のものが多く、借入期間も5年以上と長期設定される傾向が見られます。
借入期間が長ければ、月々の返済額も少なく抑えられるので資金繰りも円滑になるでしょう。
ただし借入条件などは、自治体によりまちまちです。
法人所在地を管轄している自治体では、どのような形で貸付を行っているか申し込む前に確認しておきましょう。
個人事業主は借入できる?
会社に属さずに自分でビジネスを行っている個人事業主という働き方に注目が集まっています。
ある企業が調査したところ、日本のフリーランス人口は2021年時点で1,670万人に達したといいます。
これは2018年から500万人以上増加したことになります。
また労働人口の約1/4を占めるほどになり、急成長している働き方といえます。
個人事業主も資金繰りは重要な問題で、いざというときのために借入方法を考えておくべきです。
個人事業主が融資を受けるには?
個人事業主の場合、法人化されていないので事業性資金の融資が受けられるのか不安に感じている人もいるでしょう。
結論から言えば、個人事業主でも融資先の基準をクリアしていれば借入は可能です。
しかし個人事業主の場合、少なくとも以下で紹介する2つの条件をクリアしなければなりません。
まずは開業届を出していることです。
事業を新規開始する際には、税務署に申告しなければなりません。
原則は事業開始などの事実のあった日から1カ月以内に提出しなければなりません。
しかし開業届を出していなくても、ペナルティはありません。
このため、個人事業主の中には開業届を出さずに活動している人も多いでしょう。
もし開業届を出していなければ、開業届の手続きを済ませてから融資の申し込みをしたほうがいいでしょう。
もう一つの条件は、確定申告をしていることです。
法人同様、個人事業主も事業性資金を借り入れる際に財務状況を確認できる確定申告書などの提出が求められるからです。
またそもそも確定申告をせずに納税を行っていない個人事業主には、融資しないところが多いです。
自分の資金繰り状況を把握するためにも、会計ソフトなどを使って経理作業を行いましょう。
そのうえで毎年確定申告の手続きを行い、滞納することなく納税することです。
個人事業主の借入先でおすすめなのは?
個人事業主で資金調達のためにどこかで借入したければ、日本政策金融公庫を利用するのがおすすめです。
日本政策金融公庫では、個人事業主向けのいろいろな融資制度を提供しているからです。
政府系金融機関なので収益よりも、経済の活性化などを目的にしています。
ですから金利を低めに設定し、返済期間も5年以上のものが多く借入条件に恵まれています。
また中には担保も保証人も不要で借入できるようなものも見られます。
ただし日本政策金融公庫で借り入れる際には、入念な準備が必要です。
返済計画を説明するために、数多くの資料を用意しなければなりません。
また先ほども紹介したように融資実行されるまで1カ月以上かかるので、その間の資金繰りについても検討しなければなりません。
金融機関からの融資を検討するのなら、信用金庫での借入を検討するといいでしょう。
信用金庫は地域の繁栄を目的とした金融機関で、中小企業や個人事業主向けの融資に力を入れているからです。
メガバンクなど大手の銀行は、主に大手企業向けに融資を行っています。
個人事業主のような経営基盤の盤石ではないところへの貸付には積極的ではありません。
銀行での借入を希望するなら、地元の信用金庫への申し込みを優先してください。
法人カードのキャッシング機能を利用して資金調達するのも一つの方法です。
法人カードは個人事業主でも作ることが可能です。
すでにクレジットカードを持っている人も法人カードを作れば、経費とプライベート用の支払いを分けられるので帳簿管理が楽になります。
また法人カードを使って仕入れ費用などの経費支払いをすれば、その場で支払いをしなくても済みます。
1〜2カ月程度支払いを先延ばしにできるので、資金繰りの負担を軽減できます。
法人カードも個人用のクレジットカード同様、ポイント還元プログラムを用意しているところが多くあります。
これから法人カードを作るのであれば、ポイント還元率の高いところに申し込むのがおすすめです。
そのほかにも年会費や付帯サービス、カードブランドなどもチェックして法人カードを作ってください。
自治体によっては、個人事業主向けの融資制度を採用している場合もあります。
業種や用途などでいろいろな融資制度がありますので、自分が活用できるような制度が用意されていないか確認してみるのも一考です。
借入以外の方法も・事業者が資金調達する方法を紹介
事業者が資金調達する場合、どこかからお金を借りなければいけないと思っている人もいるかもしれません。
しかし資金調達の方法は、何も借入だけではありません。
事業者向けの借入以外の資金調達方法として、主に以下の手法が考えられます。
1.ファクタリング
2.クラウドファンディング
3.補助金・助成金
いずれも借入ではないので、後日返済の義務がありません。
返済の必要がないので、後々の資金繰りを考えると検討する価値は十分あるでしょう。
ファクタリング
ファクタリングとは、皆さんが抱えている売掛債権を売却する形で資金調達する方法です。
売掛金を現金化するまでに1〜2カ月かかるのが一般的です。
現金化する前にファクタリング会社に債権を売却して、予定よりも早く現金を確保する方法になります。
ファクタリングのいいところは、スピーディに現金化できる点にあります。
早ければ、申し込んだその日のうちに現金化できる場合もあるほどです。
またファクタリングは売掛債権を買取してもらうサービスのことです。
たとえ売掛先が倒産して債権回収できなくなったとしても、ファクタリング会社から債権の立て替えを求められる心配はありません。
事業者向けのファクタリングは買取サービスであり、借金ではありません。
ですから信用情報に影響しないのもおすすめのポイントです。
今後銀行融資を利用したい場合でも、審査で悪影響をもたらすことは考えにくいでしょう。
ファクタリングには2社間と3社間の2通りの方法があります。
2社間とは利用者とファクタリング会社のやり取りで、売掛先に知られることなく債権を現金化できます。
しかし2社間の場合、手数料が高くつきます。
だいたい10〜30%が相場といわれているので、正規の方法で現金化するのと比較して調達できる金額はかなり少なくなります。
一方3社間の場合、手数料の相場は2〜20%です。
2社間と比較して手数料は低めです。
しかし3社間の場合、売掛先企業の承諾が必要になります。
ファクタリングの利用が売掛先企業に知られると、マイナスの影響を与えかねません。
「ファクタリングを利用しなければならないほど資金繰りに行き詰っているのか?」と思われ、取引内容の見直しを求められる可能性があります。
クラウドファンディング
事業者向けのクラウドファンディングとは、ネットを通じて事業プランなどを説明します。
そしてその計画に賛同した不特定多数の人から出資してもらう方法です。
比較的最近出てきた資金調達方法といえます。
クラウドファンディングの場合、銀行融資で審査落ちしてしまうような事業でも出資者を募ることができる可能性があります。
銀行では収益の不確定性で融資を拒否されても、ネット上では賛同してくれる人も出てくるかもしれません。
クラウドファンディングの場合、出資者に対して何かしらのリターンを提供することが多いです。
ただし必ずしも金銭である必要はありません。
今回提案している商品やサービスをリターンとしてもかまいません。
また中には「寄付型クラウドファンディング」といって、純粋に寄付でお金を集めてリターンしない方法もあります。
ただしクラウドファンディングの場合、「いつまでにいくら集める」と目標を設定しなければなりません。
もしこの目標に到達できなかった場合、資金確保できない恐れがあります。
つまりクラウドファンディングを成功させるためには、事業に賛同してくれる人を一定数確保しなければならないわけです。
クラウドファンディングを成功させるためには、「これなら出資できる」と見ている人に思わせなければなりません。
そのためには事業計画を詳細に策定し、出資することでどのようなメリットが期待できるか説明しましょう。
ネットを通じて、出資者を説得するようなイメージで検討してみましょう。
補助金・助成金
自治体によっては、事業者・法人向けの補助金や助成金制度を進めている場合もあります。
補助金や助成金は給付なので、融資ではありません。
つまり後々返済する必要のないお金なので、資金繰りが円滑になります。
ただし補助金や助成金の趣旨と自分たちの進めている事業がマッチしているかは慎重に検討する必要があります。
またどのような補助金や助成金事業を行っているかは、自治体によってまちまちです。
所在地を管轄している自治体によっては、利用できる補助金や助成金がないかもしれません。
興味のある人は、とりあえず自治体のホームページでどのような補助金や助成金の募集が行われているか、チェックしましょう。
事業者がより確実に借入するために気を付けること
事業者が資金調達するにあたって、借入できる場合もあれば審査結果が芳しくなく融資を断られる場合もあります。
事業者が同じ金融機関に申し込む場合でも、事前準備がしっかりできているかどうかで審査結果が異なる可能性もあり得ます。
より借り入れやすくするためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
1.綿密な事業計画書を作成する
2.財務状況を詳細に説明する
3.認定支援機関に相談する
4.必要最低限の借入額にする
この4つのポイントがなぜ審査通過しやすくなるのかについて、以下で解説します。
綿密な事業計画書を作成する
事業者・法人向け融資の審査を進めるにあたって、事業計画書の提出を求められるでしょう。
実はこの事業計画書の出来次第で、融資の判断が決まるといっても過言ではありません。
そもそも融資にあたって審査するのは、貸し出したお金が回収できるかどうか見極めるためです。
事業計画書をもとに、どの程度の収益が出るか、安定した利益が見込めるかを判断するので審査結果に大きな影響力を持ちます。
事業計画書を見て「これなら今後も安定して収益をあげられるだろうな」と相手が思えば、融資を受けられる可能性もアップするわけです。
そこで事業計画書を作成する際には、具体的かつ詳細に作成することが大事です。
会社概要や手掛けている事業内容、商品の概要といった基本情報はもちろんのこと、競合他社の状況などの環境に関する情報、自社の強み、マーケティング戦略や事業展開に関するスケジュール、今後の財務計画など全体的に説明できるような事業計画書を作成することです。
プラスして、市場調査のデータなどを添付すると事業計画書に書かれていることの裏付けになり、説得力も増します。
財務状況を詳細に説明する
事業者向けの融資の審査にあたっては、事業計画書のほかにも財務関係の書類の提出も必須です。
財務状況が健全でなければ、お金を貸し付けても返済が滞る可能性が高く不良債権化してしまうリスクも高いといえます。
そこで財務関係の書類をしっかり準備し、財務状況が健全であることをアピールしましょう。
財務状況が健全であると判断されれば、信頼できる法人であるとなり融資される可能性も高まります。
財務関係の書類として、損益計算書や貸借対照表の提出が求められるでしょう。
損益計算書や貸借対照表に不備があれば、たとえ手掛けている事業が魅力的でも財務に不安ありと判断され、融資を見送られるかもしれません。
財務関係の書類を提出する際には、各項目に抜けや漏れがないか確認しましょう。
売上総利益や預金、在庫、売掛金、純資産などはどの金融機関でもチェックされるはずです。
こちらの項目に問題はないか、申し込む前に確認しておきましょう。
資料に関して問題があるほかにも、収益がマイナスだと返済能力に問題ありと判断され、融資が否決されるかもしれません。
しかしあくまでも一時的なマイナス収支で、手掛けている事業に将来性があると判断されれば、融資を受けられる可能性が出てきます。
先ほど紹介した事業計画書と合わせて、きちんとした書類を用意できれば借入できる確率も高まるでしょう。
認定支援機関に相談する
こちらは日本政策金融公庫での借入を検討している事業者におすすめの方法です。
認定支援機関を利用すれば、審査通過する確率を高められるといわれています。
認定支援機関とは、国が認定している機関のことで経営に関して一定レベル以上の専門知識や実務経験を有していることを証明しています。
認定機関として、商工会や商工会議所、金融機関などのほかにも税理士や弁護士、公認会計士、中小企業診断士の個人も含まれます。
認定支援機関では、経営に関する相談を受け付けています。
そしてそれぞれの事情を考慮して、経営面でどのような部分に注意すればいいか助言してくれます。
認定支援機関に相談のうえ、機関の紹介で日本政策金融公庫に申し込むと借入できる可能性が高まります。
認定支援機関では、融資申し込みのアドバイスも行っているからです。
たとえば先ほど紹介した事業計画書の作成のアドバイスをしてくれます。
より説得力のある事業計画書が作れれば、融資を受けられる可能性も高まるわけです。
また日本政策金融公庫では、融資を申し込むと面談が実施されます。
面談でどのようなことが聞かれるのか、質問にどう回答すればいいかのアドバイスも行っています。
このように各種アドバイスが受けられるので、相手が信用力のある法人と思わせることができ、有利に手続きを進められるわけです。
認定支援機関に相談すれば、相談料がかかります。
多少コストはかかるものの、より確実に日本政策金融公庫からの公的融資を受けるためにはおすすめです。
必要最低限の借入額にする
事業者が借入をする際には、いくら必要なのか綿密に検討することです。
運転資金や設備投資など、今後いくらお金が必要になるか正確に計算します。
そのうえで自分たちがねん出できる金額はいくらほどかも見直しましょう。
必要な金額から自己資金で賄える金額を差し引いた金額が、借入必要額です。
このように具体的な金額を出しておけば、必要最小限の金額を借り入れられます。
審査の中で借入希望額も重要なポイントです。
借入額が大きくなれば、債権回収できないリスクも高まり審査も厳しくなります。
また、できるだけ借入額を少なくすれば、後々の返済負担も軽減されます。
大まかではなく、正確な借入額を出してから申し込んでください。
おすすめのビジネスローン会社比較表
それぞれの会社には独自の特徴がありますが、なかには審査を受けるハードルが比較的低く、スピーディーな融資に対応しているところもあります。特に、代表者が金融ブラックでも借入が可能なケースや、保証人・担保なしで申し込める商品もあります。
法人がビジネスローンを利用する時には、資金不足や支払い遅延による倒産のリスク、いわゆる黒字倒産を防ぐために、返済計画をしっかり作成し、資金繰りやキャッシュフローの状態を正確に把握・管理することが重要です。融資を受けるだけでなく、補助金や助成金の制度も活用すれば、財務基盤の強化や事業資産の増加にもつながります。
また、事業を続ける上では収支のバランスを毎月チェックし、人件費や設備費などの出金タイミングを調整することが求められます。必要に応じて、税理士や財務の専門家に相談して、損益計算書や収益、支払項目の状況を整理した資料を作成することも役立ちます。
例えば、在庫の売却や不要な購入の見直しを行うことで、手元に残る金を確保し、短期的な資金不足の影響を抑えることが可能です。事業活動や営業活動の中で発生する支出の増減を把握し、未来の支払いリスクを予測しながら、計画的に投資や事業の継続に必要な資金を動かすことが重要です。
ここで紹介したように、会社経営における資金管理は単なる融資利用に留まらず、制度活用やコラムでの情報収集、過去の事例分析など、幅広い方法で行うことができます。適切な管理を行い、リスクを回避しながら事業の安定した成長を目指しましょう。
| 業者名 | 融資対象 | 金利 | 入金スピード | 融資限度額 |
|---|---|---|---|---|
| アクトウィル | 法人 | 7.5%~15% | 最短即日 | 最大1億円 |
| AGビジネスサポート | 法人・個人事業主 | 3.1%~18% | 最短即日 | 1000万円 |
| ファンドワン | 法人 | 2.5%~18% | 最短即日 | 1億円 |
| デイリーキャッシング | 法人・個人 | 5.2%~18% | 最短即日 | 8000万円 |
| 株式会社オージェイ | 法人・個人 | 9.5%~18% | 最短即日 | 1億円 |
| Carent | 法人 | 7.8%~15% | 最短即日 | 500万円 |
| オリックス・クレジット | 法人・個人 | 6.0%〜17.8% | 最短即日 | 500万円 |
| ビジネスパートナー | 法人・個人 | 9.98%〜18.0% | 最短5日 | 500万円 |
| いつも | 法人・個人 | 4.8%~18.0% | 最短即日 | 500万円 |
| プロミス | 個人 | 6.3%~17.8% | 最短即日 | 300万円 |
| GMOあおぞらネット銀行「あんしんワイド」 | 法人 | 0.9%~14.0% | 最短2営業日 | 最大1,000万円 |
おすすめのビジネスローン会社概要
アクトウィル

アクトウィル株式会社は、法人向けの事業者金融です。申込は電話かメールでメールだと24時間受付しています。
必要書類はFAXで提出でき、最短即日で審査可能です。アクトウィルは低金利と大口融資が可能で、実質年率7.5%~15%と比較的低い金利で融資が受けられます。また、最大1億円の融資が受けられるため、まとまった資金の調達をしたい企業におすすめです。融資は法人契約の為ため、代表者の連帯保証のみで第三者による保証人や不動産担保は不要です。メールでの相談やお問い合わせは24時間受付してますので、営業時間外でも問い合わせられます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 7.5%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | アクトウィル株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31521号 |
| 住所 | 〒160-0022 東京都豊島区東池袋3-11-9 |
| 電話番号 | 03-5944-9168 |
| FAX番号 | 03-5944-9169 |
| 営業時間 | 平日9:00~20:00 |
AGビジネスサポート

AGビジネスサポートは、企業の成長を支援するためのビジネスローンを提供しています。AGビジネスサポートのビジネスローンは、資金調達のニーズに応じて柔軟に対応し、迅速な審査と融資を実現します。特に、中小企業やスタートアップ企業にとって、資金繰りは重要な課題です。AGビジネスサポートでは、経営者の皆様が抱える資金の悩みを解消し、事業の発展をサポートすることを使命としています。
AGビジネスサポートのビジネスローンは、用途に応じた多様なプランを用意しており、設備投資や運転資金、さらには新規事業の立ち上げ資金など、さまざまなニーズに対応可能です。審査基準も柔軟で、過去の実績や信用情報だけでなく、将来のビジョンや事業計画を重視した評価を行います。これにより、資金調達が難しいとされる企業でも、安心してご相談いただけます。さらに、AGビジネスサポートでは、専門のスタッフが個別にサポートを行い、最適なプランをご提案します。お客様のビジネスの特性や成長段階に応じたアドバイスを行い、資金調達のプロセスをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1000万円 |
| 金利 | 3.1%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | AGビジネスサポート株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01262号 日本貸金業協会会員第001208号 |
| 住所 | 東京都港区芝2丁目31-19 |
| 電話番号 | 0120-027-120 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 平日9:30~18:00 |
ファンドワン

ファンドワン株式会社は、東京都豊島区南大塚に本社を構える、事業者向け金融サービスを提供する企業です。2020年1月に設立され、資本金5,000万円を基盤に事業を展開しています。同社は、全国の事業主に対し、迅速かつ柔軟な与信判断と安心の金利帯で資金調達を支援しています。
提供するサービスには、無担保の事業者ローンや、不動産・売掛債権を担保としたローン、車担保融資、介護・診療報酬担保融資など、多様な商品が含まれています。最短40分のスピード審査や、最大1億円の大型融資が可能である点が特長で、赤字決算や税金・社会保険料に課題を抱える事業主にも柔軟に対応しています。
ファンドワン株式会社は、単なる資金提供に留まらず、中小企業の成長を支援し、地域社会や日本経済全体の活性化に貢献することを使命としています。これまで、経営難に直面した多くの企業の資金繰りや経営再建をサポートしてきました。同社は、経験豊富なスタッフが最適なプランを提案し、事業主とともに成長を目指すパートナーとして信頼されています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 2.5%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | ファンドワン株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(2)第31816号 |
| 住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚二丁目39-11 ヒサビル6階 |
| 電話番号 | 03-5395-8888 |
| FAX番号 | 03-5395-8800 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
デイリーキャッシング

株式会社デイリープランニングは、個人のお客様から法人のお客様まで幅広いニーズに対応したローンサービスを提供している企業です。主に「フリーローン」「おまとめローン」「不動産担保ローン」「ビジネスローン」を取り扱い、それぞれの状況に最適な融資プランを提案しています。
同社のサービスは、全国どこからでも利用可能で、急な資金需要に柔軟に対応します。特に、急な出費や資金繰りの困難を抱える方々に、迅速かつ確実な融資の手続きを提供し、お客様の生活やビジネスを支えています。
さらに、デイリープランニングでは、融資の申し込みが簡単で、インターネットや電話、店舗での手続きもスムーズ。お客様一人ひとりの状況に合わせた親身な対応を心掛け、信頼性の高いサービスを提供しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 8000万円 |
| 金利 | 5.2%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社デイリープランニング |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(3)第31698号 |
| 住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-12徳永ビル4階401号 |
| 電話番号 | 03-6284-3674 |
| FAX番号 | 03-6284-3675 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
株式会社オージェイ

株式会社オージェイは、法人向けに多彩な融資サービスを提供する企業で、事業資金の調達をサポートします。提供する融資メニューには、無担保融資、手形割引融資、不動産担保融資、動産担保融資、ファクタリング、診療報酬担保融資などがあり、さまざまな事業ニーズに柔軟に対応しています。
同社は、急な資金調達が求められる場面でも迅速に対応できる体制を整えており、審査もスピーディで信頼性の高いサービスを提供しています。また、日本貸金業協会に加盟しており、法的にも安心して利用できることが保障されています。中小企業や個人事業主など、資金繰りに困っている事業者に対して、親身なサポートを行い、ビジネスの安定と成長を支援しています
さらに、オンラインで簡単に申し込めるため、全国どこからでも迅速で効率的な資金調達が可能です。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 9.5%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社オージェイ |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31549号 |
| 住所 | 東京都中野区中央1-32-5 青光堂ビル3F |
| 電話番号 | 03-5332-3833 |
| FAX番号 | 03-5322-3834 |
| 営業時間 | 平日10:00~15:00 |
Carent

事業資金のニーズに柔軟に応える「Carent ビジネスローン」は、スピーディーで安心の融資サービスです。中小企業や個人事業主の方々が直面する資金繰りの課題を解決し、成長をサポートします。
柔軟な条件設定:事業規模や状況に合わせた融資プランをご提案。迅速な審査:最短○日で審査完了、資金調達をスムーズに。安心のサポート体制:専門スタッフがご相談から契約まで親身に対応します。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 7.8%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社IPGファイナンシャルソリューションズ(キャレント) |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(5) 第31399号 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-24-4 WEST HILLビル5階 |
| 電話番号 | 03-5740-5087 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 |
オリックス・クレジット

オリックス・クレジット株式会社は、1979年にオリックス株式会社とフランスの大手信販会社セテレム社の合弁により設立され、オリックスグループ初の個人向け金融サービスを提供する企業として誕生しました。設立当初はショッピングクレジットや有担保ローンを中心に展開していましたが、1987年には低金利かつ高額融資が可能な「VIPローンカード」を発売し、プレミアム・カードローン市場の先駆者としての地位を築きました。
その後、貸金業法の改正に伴い、市場環境の変化に対応するため、これまで培った与信やオペレーションのノウハウを活かし、金融機関向けの信用保証事業に注力。現在では全国250社以上の金融機関と提携し、同社の主力事業の一つとなっています。
さらに、オリックス株式会社から事業を継承し、モーゲージバンク事業にも参入。「フラット35」を中心とした住宅ローン商品を提供し、新築だけでなく中古物件のリノベーション向けや地域活性化と連携した商品など、多様なニーズに応じたサービスを展開しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 6.0%〜17.8% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00170号 |
| 住所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー |
| 電話番号 | 非公開 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
ビジネスパートナー
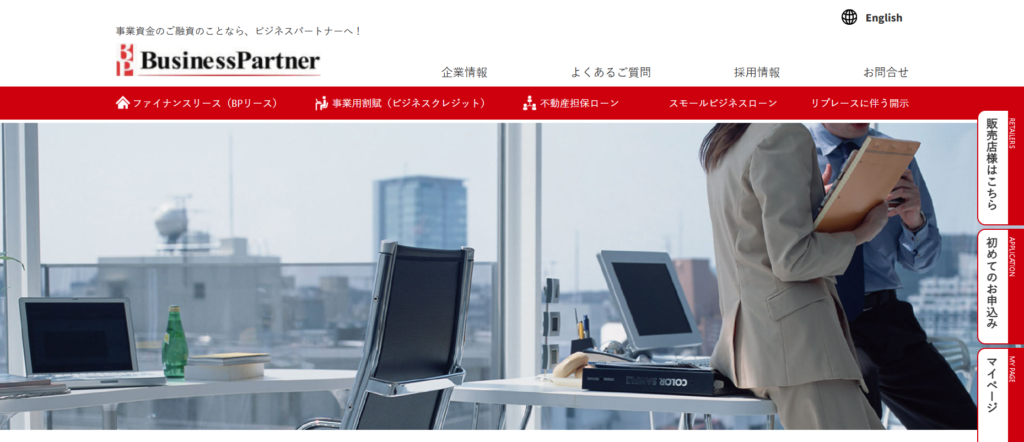
株式会社ビジネスパートナーは、1999年に設立され、東京都新宿区に本社を構える金融サービス企業です。中小企業や個人事業主向けに、柔軟な事業資金融資を提供しており、特にスピーディーな資金調達を求める事業者に支持されています。
同社の主力商品である「スモールビジネスローン」は、来店不要で契約可能な無担保ローンで、事業資金の用途に応じた自由な活用が可能です。原則として担保や保証人を必要とせず、手数料もかからないため、資金調達のハードルが低いのが特長です。また、セブン銀行ATMを活用することで、365日24時間、資金の引き出しや返済が可能な利便性の高いサービスを提供しています。
さらに、ファイナンスリース「BPリース」や事業用割賦「ビジネスクレジット」、不動産担保ローンなど、多様な資金調達の選択肢を用意。事業運営に必要な資金を柔軟に確保できるよう支援し、企業の成長をサポートしています。特に、事務処理の簡素化や全額損金処理の可能性など、経営効率を向上させるメリットも提供しています。
ビジネスパートナーは、迅速かつ柔軟な資金提供を通じて、中小企業の発展を支える信頼できる金融パートナーとして、多くの事業者に利用されています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 9.98%〜18.0% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短5日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社ビジネスパートナー |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01500号 |
| 住所 | 〒160−0022 東京都新宿区新宿6‐27−56 新宿スクエア6F |
| 電話番号 | 非公開 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
いつも
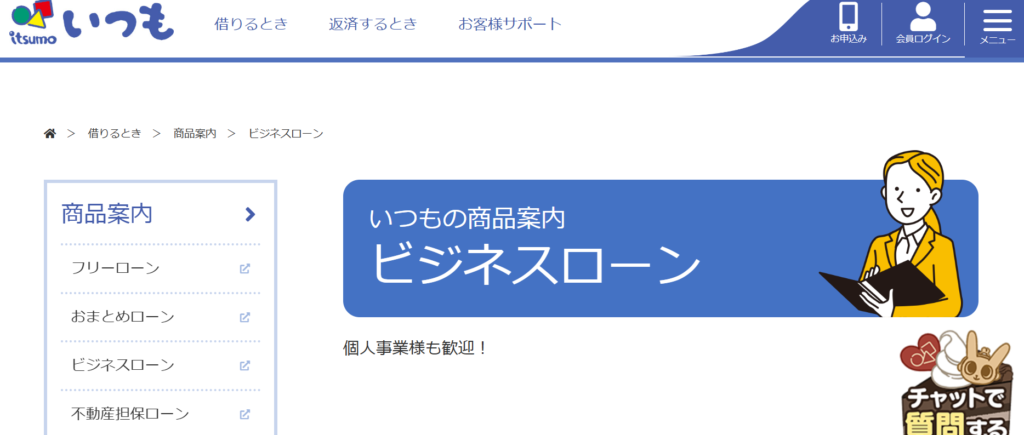
株式会社K・ライズホールディングス(ブランド名:いつも -itsumo-) は、個人および法人向けに多様なローンサービスを提供する金融会社です。主な取り扱い商品には、フリーローン、おまとめローン、ビジネスローン、不動産担保ローンなどがあります。
特に ビジネスローン は、個人事業主や法人の事業資金ニーズに対応し、迅速かつ柔軟な融資を実施。オンラインでの申し込みは 24時間365日対応可能 で、最短30分での審査・融資も可能です。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 4.8%~18.0% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社K・ライズホールディングス |
|---|---|
| 登録番号 | 高知県知事(4)第01519号 日本貸金業協会会員 第005847号 |
| 住所 | 高知県高知市杉井流5-18 |
| 電話番号 | 0570-055-126 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 不明 |
プロミス

個人事業主の資金調達をサポート!プロミス「自営者カードローン」は事業を運営する上で、急な資金ニーズ に対応できる柔軟なローンがあると心強いものです。プロミスの「自営者カードローン」は、個人事業主の方を対象 としたローンサービスで、最大300万円 まで借入可能。事業資金だけでなく、プライベートな用途 にも利用できるため、事業と個人の資金管理をスムーズに行えます。
申し込みは 24時間365日 受け付けており、インターネットから簡単に手続き可能。さらに、スピーディーな審査と融資 により、急な資金調達にも対応できるのが大きな魅力です。例えば、運転資金や設備投資、仕入れ資金 など、さまざまな用途で活用できます。また、必要書類も本人確認書類 と 事業内容を確認できる書類(例:確定申告書) のみとシンプル。手続きが簡単で、事業を営む方の負担を最小限に抑えられます。。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 300万円 |
| 金利 | 6.3%~17.8% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00615号 |
| 住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル |
| 電話番号 | (03)6887-1515 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
GMOあおぞらネット銀行「あんしんワイド」

法人の資金繰りをサポートするGMOあおぞらネット銀行のビジネスローン「あんしんワイド」は、事業資金の幅広いニーズに対応できる柔軟なローンサービスです。最大1,000万円まで借入可能で、設備投資や運転資金、仕入れ資金など、さまざまな用途に活用できます。
申し込みはオンラインで完結し、必要書類も少なくスピーディー。最短2営業日での審査・融資に対応しており、急な資金需要にも頼れるのが特徴です。担保や保証人は不要で、全国の法人が対象となっています。
| 区分 | 銀行 |
|---|---|
| 融資限度額 | 1,000万円 |
| 金利 | 0.9%~14.0% |
| 審査日数 | 最短2営業日 |
| 入金スピード | 最短2営業日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第321号 |
| 住所 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
| 電話番号 | 03-3461-5000 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:00(オンラインは24時間受付) |
事業者借入に関するまとめ
ここで紹介したように、事業資金の借入方法は多種多様です。
それぞれ異なる特徴があるので、その時々の状況でベストな選択肢は変わってきます。個人事業者の方も含め、事業者は自分たちの事情に合わせて、最適な資金調達方法を検討してください。
また、ファクタリングをはじめ、借入以外で資金調達する方法もあります。貸付ではないため、後々の返済義務が発生しません。場合によっては、資金の転貸借や転貸を活用できるケースもありますので、特定の目的に合わせて柔軟に選ぶと良いでしょう。














