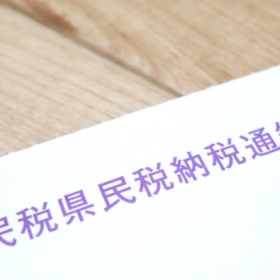事業者がとることのできる資金調達方法にはいろいろな手法があります。
今回紹介するABL(売掛債権担保融資)とは「売掛債権担保融資」と呼ばれる方法です。
商品在庫や売掛金などの流動性の高い資産を担保にして融資を受ける資金調達方法です。
不動産など資産を持たない企業でも、売掛金や商品在庫などは有しているところも多いでしょう。
より多くの法人が資金調達できる方法として注目を集めています。
ABL(売掛債権担保融資)の場合、融資実行された段階で法務局に債権譲渡登記の手続きを行います。
債権譲渡登記とはどのようなものか、手続きをする際に注意すべきポイントについてもまとめました。
目次
ABL(売掛債権担保融資)の流れについて紹介
ABL(売掛債権担保融資)はどのような手続きで資金調達を行うのでしょうか?
多少金融機関によって手順は異なるかもしれませんが、例えば売掛金を担保にする場合以下のような流れになります。
1.融資の申し込み
2.審査
3.契約書の締結
4.融資実行
5.定期報告
それぞれどのようなことをやるのかについて、以下で解説します。
融資の申し込み
他の借入同様、まずは融資の申し込みを行います。
売掛金を担保にする場合、複数売掛債権を持っているのであればどれを担保として差し出すかを検討する必要があります。
申し込みをする際には売掛先に関する情報を提供しなければなりません。
売掛先との取引履歴なども提示する必要があると思ってください。
そのほかに従来の融資申し込みと同様で、決算書などの必要書類を準備しなければなりません。
ここでおすすめなのが、売掛金の入金口座とABL(売掛債権担保融資)申し込みの口座が同じ金融機関であることです。
そうすれば、金融機関としてもお金の流れが把握しやすいからです。
ABL(売掛債権担保融資)を融資している金融機関の中には、入金がない売掛先の場合申し込み金融機関を入金口座として指定しなければならないとしているところもあります。
審査
申し込みが受理されると、審査が実施されます。
もちろん申し込み人である法人の信用力などについて調査されます。
決算状況はどうなっているのか、過去に金融事故を起こしたことがないのかなどについて調査されます。
加えて売掛先企業に関する調査も実施します。
もし債務者が返済できなかった場合、売掛債権を担保としてとって現金化する必要があります。
ところが売掛先企業の経営状況が安定していないと、売掛金を回収できない恐れがあります。
そのようなことにならないために、売掛金の信用力についても調査するわけです。
契約書の締結
申し込みした法人や売掛先企業の調査を行って、最終的に融資の可否の判断を出します。
審査承認するにあたって、条件の付く可能性もあります。
例えば信用保証協会の保証を付けることなどの条件付き融資の場合もあります。
信用保証協会の保証を付けるにあたって、保証料を負担しなければなりません。
審査にかかる期間ですが、金融機関によってまちまちです。
3週間程度かかる場合もあれば、最短即日融資などスピーディさを売りにしているところも見られます。
融資実行
審査承認されれば、金銭消費貸借契約書をはじめとした契約を金融機関とかわします。
金融機関の方でどのような書類を提出すればいいか案内がありますので、その指示に従ってください。
またこの契約手続きの際に、譲渡担保である売掛債権の差し入れ手続きも進めていきます。
それを受けて金融機関では、債権譲渡登記手続きを法務局にて行います。
ここまでの事務手続きが完了したところで、融資は実行されます。
定期報告
融資実行後も金融機関とのコンタクトは必要です。
返済や売掛債権がどうなっているのかなど、定期的に情報を提供しなければならないからです。
具体的には、売掛先の債権の残高に関する情報などを提供する形になります。
債権譲渡登記と動産譲渡登記
ABL(売掛債権担保融資)では売掛債権もしくは在庫商品を担保にして、融資を受ける資金調達方法です。
ABL(売掛債権担保融資)の場合、譲渡登記を法務局で行わないといけません。
この時何を担保にして融資を受けるかによって、登記手続きの方法が変わってきます。
売掛金の場合には債権譲渡登記、在庫商品であれば動産譲渡登記を行います。
それぞれどのような登記手続きかについて、ここで詳しく見ていきます。
債権譲渡登記
売掛金をはじめとした金銭債権を担保にABL(売掛債権担保融資)による融資を受ける際には、債権譲渡登記と呼ばれる手続きを行います。
今では、現在すでに発生している売掛金以外にも、将来発生するであろう売掛金も担保として差し出せるようになりました。
このため、売掛債権を用いたABL(売掛債権担保融資)の利用も広く普及しつつあります。
ちなみに売掛先が複数ある場合でも、一括して手続きを取ることが可能です。
しかも事前通知なしでかまわないので、比較的端的に手続きできるところも債権譲渡登記を用いたABL(売掛債権担保融資)は人気です。
もし売掛債権を担保にして借入するとなると取引先が不安に感じる可能性もあります。
取引を見直してくるところも出てくるかもしれません。
しかしABL(売掛債権担保融資)の場合、債権譲渡登記を行ったことは基本的に取引先に知られることはありません。
取引先に内緒で手続きできるのは魅力です。
ただし債権譲渡登記の管轄法務局は東京法務局のみになっているのは、デメリットといえます。
東京法務局の債権登録課が受付窓口になるので、地方によっては手続きが面倒になりかねません。
動産譲渡登記
ABL(売掛債権担保融資)の担保として代表的なものとして、在庫商品をはじめとした動産も考えられます。
もし在庫商品を担保として差し出してABL(売掛債権担保融資)による借入をするなら、動産譲渡登記と呼ばれる手続きが必要です。
動産譲渡登記ではその時点で倉庫もしくは店舗に存在している在庫商品はもちろんのこと、場所と商品を特定できれば後々納品される在庫商品を対象に担保にできます。
在庫になっている商品がお客さんに売れたとします。
お客さんの手に渡った在庫商品は、金融機関の担保の効力は及びません。
ですからお客さんがせっかく購入した商品が、担保として金融機関を差し押さえられる心配はありません。
ただし動産譲渡登記についても、管轄法務局は東京法務局のみとなっています。
ですから首都圏以外の地方で利用する場合には、手続きに少し時間がかかる恐れがあります。
債権譲渡登記における注意点
債権譲渡登記の制度は比較的新しいものです。
スタートしたのは平成10年10月1日です。
しかし登記申請件数は年間4万件に上るほど、ポピュラーな手続きになっています。
第三債務者が不特定だったり、債権譲渡の事実を知られたりすることなく登記手続きができるからです。
しかし債権譲渡登記を行うにあたって、注意しなければならないポイントがあります。
どのようなことに注意すべきか、どう対処すればいいかについてまとめましたのでABL(売掛債権担保融資)を利用する際の参考にしてください。
誤字があってもそのまま登記される
債権譲渡登記について、誤りがあるかどうか法務局では調査ができません。
というのも債権譲渡担保契約書をはじめ、債権が譲渡されたことを立証する書面を添付せずに手続きできるからです。
法務局でも審査は行うものの、添付書類に不備がないか、法務局の定めるプログラム通りに作成されているかだけをチェックします。
このため、例えば債権譲渡担保契約書に書かれている内容と異なる情報を申請データに記載してもスルーされてしまいます。
ですからもしかすると誤った情報が登記されてしまう恐れがあるので注意してください。
しかものちに登記上に何かしらの不備がある場合でも、その登記を変更もしくは更正手続きができません。
もし一度不備や誤りのある登記手続きをしてしまったら、いったんその登記を抹消申請しなければなりません。
そのうえで、再度新規で正しい情報の記された債権譲渡登記申請手続きをする形になります。
このように不備があった状態で登記手続きを完了させると、二度手間になってしまうので注意が必要です。
契約書の中でも債権額や譲渡日、第三債務者の記載などには誤りがないか確認しておく必要があるわけです。
債権譲渡登記の確認方法
債権譲渡登記は、不動産登記や商業登記のようなポピュラーなものとは制度そのものが異なります。
債権譲渡登記の内容は、債権譲渡登記概要記録事項証明書で確認することができます。
登記情報なので、債権譲渡登記に関しては基本誰でも確認できます。
ちなみに登記事項証明書にも債権譲渡登記を行った旨は記載されます。
どのようなことが登記されるかですが、以下のようなことが登録されているはずです。
・譲渡人と譲受人の本店や商号
・債権の総額
・登記年月日
・登記番号
・登記原因並びにその日付
・登記の存続期間の満了年月日
他の登録手続きと同様で、登録免許税を支払わないといけません。
この登録免許税の取り扱いがどうなるのか金融機関と十分話し合っておきましょう。
債権譲渡手続きを取引先に知られるリスクについて
ABL(売掛債権担保融資)の手続きをするにあたって、売掛先に通知することはありません。
このため、売掛先に債権譲渡について知られることなくABL(売掛債権担保融資)による借入れが可能です。
しかし債権譲渡登記を行った場合、登記事項証明書に記載されます。
登記されれば、基本誰でもその情報を目にできます。
ということは通知がなくても、取引先に債権譲渡した事実を知られるリスクは残ります。
取引先に知られるのはまずいと思っているのであれば、金融機関に相談してみるといいでしょう。
つまり債権譲渡登記しない形での取引はできないか、確認してみてください。
POファイナンスの活用も検討しよう
法人の資金調達方法はいろいろと出てきています。
近年注目されている資金調達方法の一つとして、POファイナンスがあります。
POファイナンスにはABL(売掛債権担保融資)と異なるポイントがありますので、どのような特徴を有した資金調達方法かについてここで解説します。
POファイナンスとは
POファイナンスとは、企業間の注文情報を電子記録債権化するのが特徴です。
電子記録債権化されたものを譲渡担保として金融機関に差し出します。
そして金融機関は融資を行うわけです。
フィンテックが発達したことによって、誕生した新たな資金調達手段です。
ABL(売掛債権担保融資)との違いについて
ABL(売掛債権担保融資)もファクタリングも共通しているのは、担保として差し出すのは売掛債権です。
ということは業務が終了したり、商品を販売したりして売掛金が発生しないと活用できません。
しかし大掛かりな案件で、完成するまでに長時間を要するような場合には完成するまで売掛債権は発生しません。
POファイナンスが従来のABL(売掛債権担保融資)やファクタリングと異なるのは、納品ではなく受発注の段階で融資が受けられる点です。
つまり将来受け取れる予定の代金を担保にできるわけです。
早い段階で将来の売り上げを現金化できるので、資金繰りに余裕が持てます。
過去に資金不足によって大型案件を断ったことはありませんか?
また短期の借入を銀行にお願いしたところ、融資を否認されたことはありませんか?
POファイナンスは、これらの代替として活用できるポテンシャルを持っています。
ただしPOファイナンスはまだ登場して間もない資金調達方法です。
よって対応している金融機関は決して多くないので、選択肢が限定される点にも留意しましょう。
まとめ:債権譲渡登記のやり直しのきかない点には注意しよう
もし売掛債権を担保にABL(売掛債権担保融資)の借入をした場合、債権譲渡登記の手続きが必要になります。
しかしこの債権譲渡登記、申請時点で情報が誤っていてもそのまま登記されてしまう危険性があります。
債権譲渡登記が正しい内容で記載されているかどうかは、きちんと確認しておいた方がいいでしょう。
もし誤っている場合には、いったんその登記を抹消して、もう一度新しく登記手続きをしなければなりません。
また不備のある登記だと、第三者に対する対抗力が認められないなどのリスクも起こりえます。
登記情報については、できるだけ早い段階で自分の目で確認するのがおすすめです。