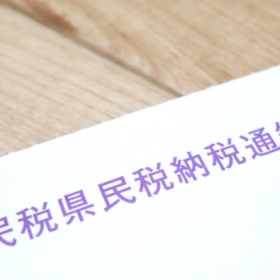診療報酬は、医療機関にとって安定した収入源である一方、実際に口座へ入金されるまでに一定の期間がかかるという特徴があります。そのため、医薬品や医療機器といった商品を提供する企業や、医療機関を支援する関連事業者にとっては、代金回収までの資金繰りが経営上の課題となりやすいのが実情です。こうした背景から、診療報酬という流動資産を活用し、ABL(売掛債権担保融資)によって早期に資金調達を行う手法が注目されています。
ABLは、診療報酬債権をはじめ、棚卸資産や在庫などの動産を担保として評価し、融資や貸越枠を設定できる点が特徴です。保証の有無や融資額、1年以内の短期資金への対応など、柔軟な資金調達が可能となるため、資金需要の波が大きい医療関連ビジネスとの相性もよいといえます。実際、医療機関向けの経営支援を行う金融機関やサービス提供会社では、診療報酬を担保としたABLを積極的に案内しています。
本記事では、診療報酬の基本的な仕組みを整理したうえで、ABL(売掛債権担保融資)を活用してどのようなフローで資金調達を行うのかを具体的に解説します。医療機関と取引のある企業はもちろん、これから医療業界への参入を検討している方も、公式サイトやサイトマップの情報と併せて参考にしていただければ、資金調達の選択肢を広げるヒントになるはずです。
目次
診療報酬をABL(売掛債権担保融資)で資金調達~1.診療報酬債権について
診療報酬とABL(売掛債権担保融資)について説明する前に、まず診療報酬そのものの理解を深めるところから始めましょう。
診療報酬とは?
日本は全国民に健康保険の加入が義務付けられていて、これを「国民皆保険」と呼びます。私たちが医療機関を受診したり、処方箋で調剤した薬を購入したりすると、窓口で自己負担分として一定割合を支払い、残りは健康保険が支払う仕組みを指します。
そして、このときに患者が医療行為に対して支払ったお金が診療報酬です。
診療報酬は一部を患者の自己負担、一部を健康保険が負担するため入金されるまでタイムラグがあります。
そのため「診療報酬とは一般企業の売上にあたり、しかも実際に受け取るまでタイムラグがある売掛金」とも表現できます。
ここまで、診療報酬についてまとめると以下の通りになります。
<診療報酬とは?>
【国民皆保険制度】
国民は、それぞれ加入する健康保険(国民健康保険、社会保険など)の保険証を提示し、自己負担分を支払うだけで医療行為(診察、治療、手術、入院、投薬など)を受けることができる。
【診療報酬の定義】
医療行為の対価として医療機関(総合病院、クリニック、診療所、薬局など)に支払われる医療費が診療報酬
【自己負担割合】
診療報酬の自己負担分は原則として3割だが、年齢により以下のとおり分かれる
(*それぞれの年齢層でも所得によっては負担率が違う場合も)
<75歳以上の自己負担割合は原則1割>
<70歳〜74歳までの自己負担割合は原則2割>
<6〜70歳未満の自己負担割合は原則3割>
<6歳(義務教育就学前)未満の自己負担割合は原則2割>
【診療報酬の計算方法】
診療報酬は、医療行為を「1点=10円」という点数で計算する
例)初診料300点+治療200点=500点×10円で医療費全額は500円
レセプト〜診療報酬の「請求書」
医療機関は、診療報酬の内容をまとめた「診療報酬明細書」を作成します。
この診療報酬明細書は「レセプト」と呼ばれ、一般企業などの請求書にあたるものです。
診療報酬は原則として1点=10円という計算方法は変わらないので、医療行為の点数が多くなるほど医療費の総額も増えるという理屈になっています。
診療報酬は「サイト3ヶ月の売掛金」
診療報酬を健康保険に請求するため、医療機関はその月のレセプトをまとめ、翌月10日までに提出します。
なお提出する先は直接健康保険ではなく、まず「審査支払機関」と呼ばれる専門部署になります。
こちらは社会保険で「社会保険診療報酬支払基金」、国民健康保険では「国民健康保険団体連合会」とそれぞれ分かれています。
この審査支払機関で、レセプトの内容などを審査して、問題がなければ健康保険に送られ、診療報酬の健康保険負担分を受け取る、という流れです。
そして、一般的にはレセプト提出の翌月20日とか25日など決まった日に、診療報酬が医療機関に支払われることになりますが、そもそもレセプトは前月の診療等などの報酬なので、医療行為の診療報酬は、実際に対応した月の3ヶ月後に支払われることになります。
<診療報酬の受け取りまで>
2023年3月に治療(*患者が支払うので、自己負担分は当月売上となる)
翌月:2023年4月10日までにレセプト提出
翌々月:2023年5月に診療報酬が支払われる
このような流れで、保険負担分の診療報酬は3ヶ月後に支払われるので、サイト3ヶ月の売掛金と同じとも言えます。また自己負担分だけは即座に現金収入となるので、少し古い表現ですが、一般的な商取引のいわゆる「半金半手(はんきんはんて):売上の一部が現金、残りが手形や売掛金という意味」のイメージに通じます。
そしてこのような点から、まだ受け取り期日が到来していない診療報酬を「診療報酬債権」と呼び、この診療報酬債権はABL(売掛債権担保融資)の対象となる売掛債権にあたるのです。
診療報酬債権流動化
ここまで説明したように、診療報酬は実際に入金されるまで約3ヶ月のタイムラグがあるため、人件費や薬など月々の支払いで資金調達が必要になる場合には、診療報酬債権を少しでも早く資金化する必要があります。
そこで、診療報酬を早期に現金化することを「診療報酬債権流動化」と呼びます。
ABL(売掛債権担保融資)で診療報酬を現金化するのも診療報酬債権流動化の一つですが、それ以外の方法もあり、以下のように分かれます。
<診療報酬債権流動化の方法>
【ABL(売掛債権担保融資)】:この記事で説明
【ファクタリング】:一般のファクタリングと同じ
【SPCによる現金化】:資金調達を目的とした特別会社(「SPC」と呼ぶ)を設立し、診療報酬債権を買い取らせることで現金化する方法
直接医療機関に融資するのではなく、SPCに対して診療報酬債権買取資金を銀行が融資して、結果的に医療機関に融資したのと同じ効果となる方法が一般的
また、診療報酬債権を小口の証券にして資金調達する「ABS:Asset Backed Securities 「資産担保証券」「債券担保証券」などとも呼ぶ)もある
診療報酬をABL(売掛債権担保融資)で資金調達~2.具体的フロー「債権譲渡登記」
診療報酬をABL(売掛債権担保融資)で資金調達できるまでにはいくつかの手続きが必要になりますが、そのなかでも重要な「債権譲渡登記」について説明します。
債権譲渡登記とは?
債権譲渡登記とは、ひとことで言えば「金銭債権(診療報酬や売掛金のこと)を譲渡したことを証明する」といった意味になります。
銀行から事業資金融資を受けるため、会社所有の不動産を担保(根抵当権など)にしたり、会社が受け取る予定の保険に質権を設定したりする(質権設定は公証人役場で確定日付を取得することで不動産の担保と同様の効力を持つ)行為に通じます。
ABL(売掛債権担保融資)では、売掛金(ここでは診療報酬)を受け取る権利を担保にして融資を受ける=金銭債権の譲渡を受ける(厳密には譲渡の予約)という流れなので、不動産担保とは異なりますが、融資した資金の保全という意味は共通です。
とはいえ、債権譲渡登記だけの特徴もあるので、わかりやすく解説します。
一般に金銭債権(売掛金や診療報酬など)を受け取る権利を他社から妨害されないよう守ることを「第三者対抗要件を具備する」と呼びます。
第三者への対抗要件を具備するには、債権者(企業が支払義務を追う相手のこと:仕入先など)に知らしめる「通知」という手段がありますが、この通知もただ伝えれば良いといったものではなく手順(具体的には確定日付のある通知書類)が必要です。
しかしながら、通知についても対象者が多くなると手間や費用の負担が大きくなります。
そこで「法人が金銭債権を譲渡した場合(これが売掛債権担保融資にあたる)には、債権譲渡登記所に登記をすれば、第三者にその旨を対抗することができる」というのが債権譲渡登記の意味になります。
債権譲渡登記制度は平成10年より実施され、ABL(売掛債権担保融資)や売掛債権流動化といった、法人の資金調達手段をスムーズに行うために制度として広く利用されています。
なお債権譲渡登記を取り扱う場所は限定されていて、東京法務局(正式には「東京法務局民事行政部債権登録課」)だけが、全国の債権譲渡登記を取り扱っています。
ここまでの説明と、その他債権譲渡登記の特徴をまとめると以下のとおりです。
<債権譲渡登記について>
債権譲渡登記の意味
法人の行なう金銭債権の譲渡を登記することで、第三者対抗要件を具備できるとしたのが、債権譲渡登記制度
具体的な方法
登記されると「債権譲渡登記ファイル」にその内容が記録される(不動産登記の登記簿と同義)
法的根拠
債権譲渡登記ファイルに記録されることで、第三者に対しては確定日付のある証書で通知があったものとみなされ、これにより第三者対抗要件が具備される(民法第467条【参考②】)
法人だけが債権譲渡登記できる
債権譲渡登記ができるのは法人のみ
債権譲渡登記手続き
債権譲渡登記の手続きは、法人の代表者など当事者でも申請することは可能ですが、揃える書類や手順などに不慣れなことで間違いを防ぐため、専門家である司法書士に代行申請を依頼するのが一般的です。
そこで、ここからの説明は司法書士に債権譲渡登記の手続きを依頼したという前提でお話していきます。
以下、事務的なフローです。
<債権譲渡登記の事務フロー>
必要書類を揃えて、 東京法務局民事行政部債権登録課に申請する
申請方法は書面の持参、郵送、オンライン申請がある
書面に変えて、必要書類を記録したCDロムの持参・郵送も可能
オンライン申請は専用URLにアクセスし手続きが完了
原則、登記申請日に登記が完了する(申請時間と混雑状況によっては翌日以降)
登記の補正(提出後、間違いに気づき修正する)は不可
したがって、申請日当日に取下げをして、改めて再申請する
登記が完了したあとは、内容の変更登記不可
(登記などの具体的な内容は、必ずご自身で公式HPや司法書士に確認してください)
債権譲渡登記費用について
債権譲渡登記に必要な費用と金額は概算で以下のとおりです。(筆者調べ)
<債権譲渡登記の概算費用>
登録免許税:1件あたり7,500円
証明書等取得費用:1通あたり300円
司法書士報酬:10万円台〜20万円台
司法書士報酬は、司法書士によって異なりますし、登記の件数などによってもまちまちなので、具体的に検討する際には必ずご自身で確認してください。
診療報酬をABL(売掛債権担保融資)で資金調達に活用するポイント~まとめ
今回は、診療報酬をABL(売掛債権担保融資)によって資金調達に活用する際のポイントについて解説してきました。医療機関と取引を行う事業者にとって、診療報酬は安定性の高い債権である一方、入金までに時間を要するため、資金繰りや貸付条件の検討が重要になります。ABLを活用することで、診療報酬を譲渡担保として設定し、所定の限度内で資金を確保できる点は大きなメリットといえるでしょう。
実際の申込にあたっては、金融機関や信用保証協会が提供する各種サービス内容や、保証料・利率・保証期間などの条件を個別に確認する必要があります。場合によっては信用保証協会の承諾や特約が付されるケースもあり、返済方法や使途、計上のタイミングについてもあらかじめ定めることが求められます。また、管理体制が不十分なまま利用すると、想定外の責任や注意点が生じる可能性もあるため、資料や案内ページ、一覧情報などを通じて最新の情報を随時確認することが大切です。
診療報酬を活用したABLは、数十万から数百万、場合によっては数千万単位(万単位以上)の資金調達が可能となるケースもあり、事業承継や新たな取引拡大を見据えた資金戦略にも有効です。当該スキームは一律ではなく、事業内容や取引形態に応じて貸付条件が異なるため、自社の方針や中長期的な計画に照らし合わせて検討することが重要です。本記事が、診療報酬ABLを検討する際の参考情報として、みなさんの判断材料の一つになれば幸いです。