周りの経営者仲間などから「税務調査を受けた」という報告を聞くと、「自社もいつかは税務調査を受けることになるのか」と気になってしまう経営者の方も多いことでしょう。
ましてや、国税庁が明確に「税務調査対象の基準」を定めているわけではないので、一体どういう基準で税務調査の対象に選ばれるのか分からず、急な要請が来るとアタフタしてしまうものです。
ただ、明確な基準こそ定められてはいないものの、これまでの傾向からある程度の基準を推測することは可能であり、それを知っておけば税務調査に対する気構えを持つことができます。
そこで今回は、税務調査の対象はどのようにして決められているのか、また税務調査の対象になりやすい事業者や業種の特徴についても解説していきたいと思います。
目次
税務調査とは?

税務調査とは、納税者が適切に納税を行なっているかを確認する調査であり、国税庁の管轄下組織である税務署などにより実施されます。
主な調査内容は、事業内容や過去の帳簿の確認など。それらに関して、税務職員から受ける質問に答えるといったことを行います。
毎年、全法人のうち3%前後の法人が調査対象として選出されているほか、個人事業主についても、およそ1%が対象となるようです。
税務調査の種類
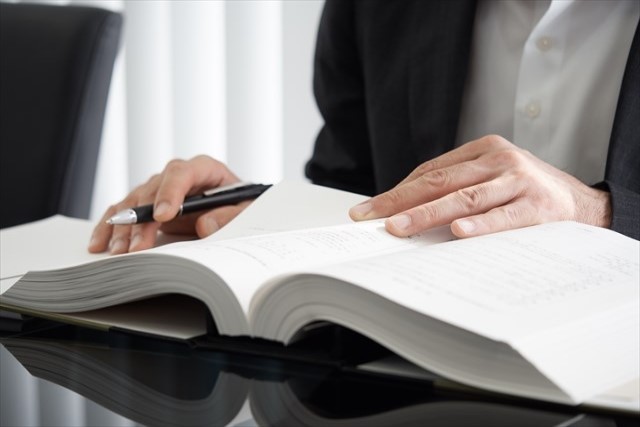
税務調査には大きく分けて2種類あります。
ひとつは「強制調査」です。
強制調査は、「マルサ」とも呼ばれる国税局査察部が裁判所の令状に基づいて実行する調査であり、調査対象者はいかなる事情があっても拒否することはできません。
もうひとつは「任意調査」です。
任意調査は、強制調査のように令状に基づいて行われるわけではなく、調査対象者の協力のもとで行われる調査であり、税務調査というと、一般的にはこちらの任意調査を指します。
「任意」と名付けられているため、仮に調査の申し入れがあっても拒否できるようにも思えますが、国税庁の管轄下にある税務職員には税務調査を行う権限が法的に認められているため、申し入れを拒否したり、嘘の答弁を行うなどした場合には罰則を受ける可能性があります。
したがって、任意調査も強制調査と同じように、実質的には「強制的」に行われる調査であるといえるため、法人や個人を問わず事業を行なって納税する以上、税務調査は避けて通れないものということになります。
税務調査対象の選出方法

では、税務職員はどのようにして税務調査の対象事業者を選出しているのでしょうか。
これは、主にKSK(国材総合管理)システムと呼ばれるデータベースを用いて行われています。
KSKシステムは、全国12箇か所の国税局と524か所の税務署をネットワークで結んで各事業者の情報や税の申告と納付事績を一元管理しており、ここに登録された情報に異常値が見られた場合に税務調査対象の候補となる仕組みとなっています。
ただしKSKシステムで異常値が検出されたからといって、即座に税務調査を実行するわけではありません。
KSKシステムの活用とあわせて、税務職員による調査や分析を行うなど、人為的な作業も行われることにより最終的な税務調査対象の事業者を選出することになります。
税務調査の対象になりやすい事業者

次に税務調査の対象になりやすい事業者や業種についてみていきましょう。
・10年以上、税務調査を受けていない事業者
KSKシステムの数値や税務職員の調査・分析によって対象事業者が選出されるため、一概には断言できませんが、法人の場合、税務調査は通常4〜5年に一度の頻度で行われるといわれています。
したがって4〜5年、長くても10年以上にわたって税務調査が行われていないという法人は、近いうちに対象となる可能性が高いということがいえます。
・短期間で売上や経費が大幅に増加した事業者
短期間で業績が大幅にアップすることは、事業者にとっては喜ばしいですが、それは同時に税務調査の確率が高まるということにもなります。
売上や経費が例年に比べて大きく増加していれば、KSKシステムは事業者単体としてのデータのみならず、同業種や同規模の事業者のデータとも比較して異常値として検出します。
そうなれば、一気に税務調査の対象になる可能性が高まるといえるでしょう。
また、メディアやSNSなどで取り上げることによって急激に知名度が向上したり、突然、企業活動を活発化させた事業者や業種などもマークされやすいといわれます。
・不正発見割合の高い業種
国税局では、税申告に関して不正発見割合の高い一部の業種を「重点業種」としてマークしており、該当業種の事業者は税務調査の対象になりやすいといわれています。
具体的には以下のような業種が挙げられます。
| ・飲食業 ・管工事業 ・土木建築工事業 ・金属製品製造業 ・自動車修理業 ・電気・通信事業 ・土木工事業 ・漁業・水産養殖業 ・廃棄物処理事業 ・貨物自動車運送業 |
また、近年ではアフィリエイトやオークション、FXや仮想通貨など、インターネット取引に携わる業種や事業者もマークの対象になりやすいようです。
過去の税務調査で不正を指摘された事業者

過去に税務調査で指摘を受けたり、重加算税を課されるといった処罰を受けていたりする事業者は、たとえKSKシステムで異常値が検出されなくても、数年にわたってマークが続けられることになります。
したがって、通常は4〜5年のうちに一度行われるといわれる税務調査ですが、改善の確認を目的として、2〜3年後などの短いスパンで再調査される可能性も十分にあると考えられます。
まとめ

今回は、税務調査の対象事業者が選出される仕組みや、対象になりやすい事業者の特徴、業種について解説しました。
税務調査の対象事業者は、KSKシステムというデータベースに登録された数値や情報を基に、税務職員の調査や分析が加えられることによって選出されます。
税務調査の申し入れは、ある日突然にやってくることもありますが、売上や経費を正しく計上し、適切に税申告を行なっていればなにも恐れることはありません。
また、実際に調査が行われる際には毅然と対応できるよう、顧問税理士に税務調査の内容や質問事項などを確認するなどして準備をしておくのも得策だといえるでしょう。















