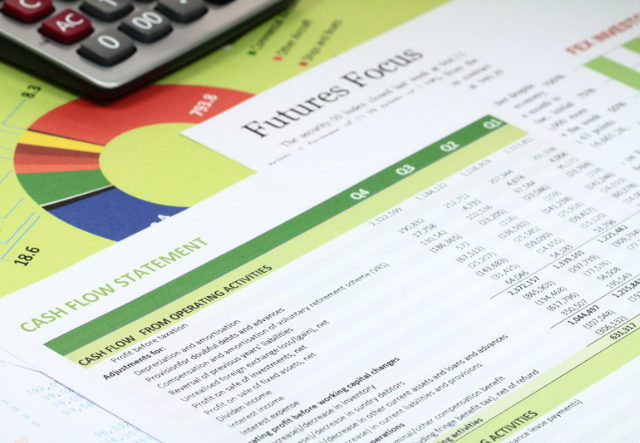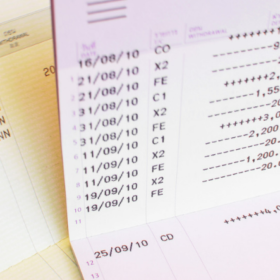中小企業が経営を存続させるためには、資金不足に陥らないように資金繰りをどう円滑に進めていくかがポイントになります。
たとえ黒字でも、資金繰りの悪化が原因で倒産してしまう企業もあるからです。
中小企業の経営者の中には、資金繰りで頭を悩ませている方も多いでしょう。
ここではなぜ資金繰りが悪化するのか、そして資金繰りの方法についてまとめましたので、参考にしてください。
目次
中小企業が資金繰りを必要とするタイミング
中小企業の資金繰りは、基本常に必要です。
しかし会社の段階によって、必要度は変動します。
会社は成長初期・拡大期、安定期の3つのステージに分類されます。
この中でも資金繰りが厳しくなるのは、成長初期です。
成長初期は事業を軌道に乗せる、研究開発を進めるなど、何かとお金が必要な段階です。
一方でまだ実績が十分とはいえないので、資金調達先を確保するのが難しいでしょう。
実際中小企業の中には、ここで十分な資金を確保できずに、事業の継続に挫折する企業も多数あります。
資金繰りが悪化する理由とは?
資金繰りが悪化していて頭を悩ませているのであれば、そもそもなぜ資金繰りに苦しむのか、その原因を明確にすることが重要です。
簡単にいえば入ってくるお金が減少した、もしくは出ていくお金が増加している、この2点が原因となります。
入るお金の減少
以前と比較して、会社に入ってくるお金が減少すれば資金繰りが立ち行かなくなるでしょう。
その原因として、いくつかが考えられます。
まずは売り上げの減少です。
売り上げが減少すれば、運転資金に回せるお金がなくなります。
季節や天候で、売り上げが減少している業界もあるでしょう。
ふたつ目の要因として、費用の増加が考えられます。
仕入れ費や販売管理費が増加すれば、収益率がダウンします。
その結果利益が減少して、経営のために回せるお金も減少するでしょう。
最後は売掛債権の回収に問題があるからです。
売掛金の回収までに時間がかかれば、本来入ってくるお金がなかなか手に入らず、資金繰りが厳しくなります。
また貸し倒れが起きて売掛金が未回収になれば、おのずと入ってくるべきお金がゼロになってしまいます。
出ていくお金の増加
出ていくお金が増大すれば、手元に資金が残りにくくなり、経営が厳しくなるでしょう。
その理由として、まず過剰な設備投資があげられます。
中には借金して、設備投資しようとする企業もあるでしょう。
この場合キャッシュフローの悪化のリスクも十分念頭に入れて、どうするか検討しなければなりません。
ふたつ目の要因として、過剰在庫もあげられます。
過剰に在庫を抱えている状態が続くと、キャッシュフローが悪化してしまいます。
在庫をストックしておく、場所を確保しなければなりません。
また管理のために光熱費などのコストがかかるなどで、出ていくお金が増大してしまいます。
3つ目の要因は早期支払いとなります。
自分たちがもっている売掛金の回収よりも、原材料費などの支払期限が早ければ、お金が早期に出ていってしまうでしょう。
資金繰りにマイナスの影響をもたらします。
最後の要因として、借金返済も無視できません。
先々のことを考えずに借金をすると、金利も発生して支払いが大きくなって、資金繰りの悪化を招きかねません。
今すぐできる!資金繰り改善のための対策
資金繰りというと、銀行などから融資を受けなければならないと考える人もいるでしょう。
しかし借り入れをしなくても、資金繰りが改善できるかもしれない方法はいくつかあります。
まずはこちらで環境改善できないか、検討しましょう。
借金せずに資金繰りを改善する方法として、以下のようなものがあげられます。
1.早期の売掛債権の回収
2.支払期日の条件見直し
3.資産を売却する
4.在庫を処分する
早期の売掛債権の回収
売掛金の回収が遅れると、その分手元に入ってくるべき資金のない状態が長く続くわけです。
もし売掛金の回収が買掛金の支払いよりも後になっているのであれば、回収期日の見直しを行いましょう。
先方との交渉が必要なものの、回収期日を見直すことで資金繰りを改善できる可能性はあります。
また取引先の与信管理を、しっかり行うことも必要です。
もし手形による取引をしているのであれば、現金決済に変更するなどもおすすめです。
手形の場合、不渡りによる貸し倒れリスクがどうしてもあります。
回収ルールを見直して、未回収分をできるだけなくすような努力もしてみましょう。
支払期日の条件見直し
もし買掛金の支払いが売掛金の回収よりも前になっているのであれば、売掛金だけでなく買掛金の期日の変更を、先方と交渉しましょう。
支払期日をできるだけ遅くすれば資金繰りの猶予が生じ、ゆとりをもって、お金のやりくりができるようになります。
ただし支払期日を遅らせるのは、取引先のリスクを高めることです。
先方にも十分配慮しながら、交渉を進める必要があります。
資産を売却する
手持ち資産があれば、こちらを売却することで現金化を進めるのも、ひとつの方法です。
資産がない中小企業でも、売掛金を現金化する方法があります。
のちに詳しく見ていきますが、ファクタリングという方法もあります。
銀行融資からも早期に現金化できるので、キャッシュフローの改善効果が見込めるものです。
また稼働していない不動産や設備などの、遊休資産を見直してみましょう。
現金が手元に入ってくるプラス、管理費や固定資産税の削減につながります。
出ていくお金を減らす効果も期待できます。
在庫を処分する
過剰に在庫を抱えているのであれば、こちらの処分も進めるとよいでしょう。
過剰在庫は、管理コストの拡大につながるからです。
在庫を売却すれば、その分現金も確保できます。
また在庫管理の見直しも進めてください。
売れない在庫を抱えない、在庫を短期で出すサイクルを作るような対策も進めましょう。
中小企業の資金調達方法を把握しよう
経営者であれば、資金繰りを改善するために資金をどこかから調達することも出てくるでしょう。
中小企業が現実的に資金を確保するための調達方法は、いくつかあります。
主だったものとして、以下のようなものが考えられます。
1.自己資金の活用
2.資本の増強
3.借入
4.補助金や助成金の活用
5.クラウドファンディング
6.ファクタリング
7.ビジネスローン
自己資金の活用
とくに中小企業の起業時に経営者がとる、資金調達方法といえるでしょう。
もし中小企業を立ち上げられるだけの資金を経営者が有していれば、対外的な信頼も得やすくなるというメリットもあります。
また経営者自身が資金調達すれば経営権を維持しやすくなり、シンプルな経営構造にできます。
経営者の自己資金の活用として、自分が所有している資産を売却することで現金化する方法もあるでしょう。
ただし個人の資金なので、そこまでまとまった資金を確保するのは難しいでしょう。
自己資金の活用だけでは、いずれ行き詰ってしまうリスクも高くなります。
資本の増強
中小企業の株式を発行して、投資家に購入してもらうことで、資本を増やす方法も選択肢のひとつです。
株式を購入してもらうので、これは借り入れではありません。
審査もなければ、担保や保証人を用意する必要もありません。
返済義務もないのが特徴です。
投資を確定させられれば、着実に資金調達できます。
ただし投資家に株を購入してもらうためには、それだけの信頼を勝ち取る必要があります。
実績のない中小企業だと、投資家もわざわざ自分のお金を出して、株式購入しようという気にはならないでしょう。
また投資家が一定以上の株式を保有するとなると、経営に口出しをしてくる可能性もあります。
株主とどううまく付き合っていけるかが、資本を増やすことで資金調達するためのポイントになってくるでしょう。
借入
中小企業の経営者が資金繰りといわれると、借り入れを思い浮かべる人も多いでしょう。
具体的には、金融機関からの融資を受ける手法です。
株式発行のように、経営権を脅かされるような心配もありません。
銀行からの借り入れの場合、金利も低く設定されています。
金融機関によってもまちまちなものの、1~3%ほどが相場です。
このため利息の支払いも少なく、返済負担も軽減できるメリットがあります。
出資が得られない、手元に現金化できる資産もない場合には、賢明な資金調達方法といえます。
ただし審査があり、融資を申し込んでも実行される保証のない点には、留意しなければなりません。
融資が受けられるかどうかは、その企業の信頼性にかかっています。
経営が安定している・業歴が長いなど信頼すべき要素が多ければ、融資を受けられる可能性が高まるでしょう。
しかし会社を立ち上げて間もなく、実績もなければ融資を断られる恐れもあります。
また銀行融資の場合、審査に時間のかかる点も検討しておかないといけません。
少なくても数週間、場合によっては1か月以上かかることもありえます。
融資実行されるまでに、資金がショートしてしまうことも考えられるので、注意しなければなりません。
補助金や助成金の活用
経済産業省や中小企業庁をはじめとして、中小企業の経営をサポートするために、補助金や助成金制度を導入しています。
補助金や助成金を活用することで、必要な資金を確保できる場合もあります。
原則補助金や助成金は支給制度なので、後日返済する必要はありません。
資金繰りに困っている中小企業を対象にした、公的サポートはさまざまなものがあります。
まずは事業再構築補助金です。
2022年時点でコロナ禍が続き、ロシアによるウクライナ侵攻もあり経済社会は大きく変化しようとしています。
このような変化に対応するために、事業再構築を進めたいと思っている中小企業をサポートするための、補助金制度です。
2020年4月以降の連続する6か月間の中で任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同じ3か月の
合計売上高と比較して10%以上減少した、かつ経済産業省の示す事業再構築指針にのっとり、認定経営革新等支援機関などと3~5年の事業計画書を策定することの、2点を満たすことが条件です。
最大1億5,000万円の補助に対応しています。
こちらは補助金ではありませんが、中小企業が受けやすい制度として、セーフティネット貸付制度があります。
資金繰りが一時的に悪化している、しかし中長期的に見れば回復の期待できる中小企業を支援するための制度です。
日本政策金融公庫が担当していて、設備資金や運転資金のための資金を融資してくれます。
返済期間が設備資金は15年以内、運転資金が8年以内と返済期間が長期である点も、無理のない返済計画が立てられるでしょう。
さらに3年間は据置期間となっているので、返済の猶予も設けられています。
ただし申し込むにあたって書類の作成など、手続きが煩雑な可能性もあります。
また審査の厳しいケースもありますので、注意が必要です。
審査に時間がかかり、助成金や補助金の支給が遅くなる可能性もあります。
今すぐ現金が必要という場合には、そぐわない資金調達方法になるかもしれません。
クラウドファンディング
最近注目を集めている手法として、クラウドファンディングがあります。
インターネットを利用して、不特定多数の人から資金を集める方法です。
実際中小企業がクラウドファンディングを介して、新事業を展開したり開発を進めたりした実績も増えています。
どのような企画を打ち出せば資金が集まりやすいかも見えるので、資金調達とマーケティングを同時並行で行えるのも、魅力のひとつです。
ただしクラウドファンディングの場合、目標金額を設定しなければなりません。
資金が十分集まらず、目標金額に到達しないと資金確保できない恐れもあります。
人々が出資しようと思えるような企画を、入念に準備する必要があります。
ファクタリング
近年中小企業の指揮調達方法として注目されているのがファクタリングです。
ファクタリングは、売掛金を早期に現金化する手法です。
ファクタリングを利用するメリットとしてまずあげられるのは、早期の現金化です。
銀行融資だと早くても2~3週間程度、公的融資に至っては1か月以上審査に時間がかかります。
しかしファクタリングであれば、最短即日現金化も可能です。
今すぐ現金が必要という経営者にとっては、このスピーディさがありがたいでしょう。
融資やビジネスローンを利用した場合、負債として会計処理しなければなりません。
一方ファクタリングはあくまでも売掛金の現金化なので、負債扱いになりません。
貸借対照表に負債として記述しなくてもよいのは、今後融資をお願いする際に審査にマイナスの影響がなくなります。
また借金ではないので、信用情報にファクタリングを利用した旨が記載される心配もありません。
ファクタリングにはメリットがある半面、注意すべきポイントがあります。
まずファクタリングを利用する際には、手数料が発生します。
こちらがファクタリング会社の利益になるわけです。
ファクタリング会社によって、手数料はまちまちとなっています。
なかでも2社間ファクタリングの場合売掛金額の15~30%、3社間ファクタリングだと1~9%が相場です。
ビジネスローン
ビジネスローンも中小企業の資金繰りの手法の中でしばしば使われる方法です。
法人や個人事業主にビジネス用途で融資するローンで、担保は必要ありません。
銀行のほかにも信販会社や消費者金融の中でも取り扱っているところがあります。
ビジネスローンのおすすめポイントは、審査期間の短いところです。
銀行融資の場合、1か月前後かかってしまって融資が実行される前に資金がショートしてしまうこともあり得ます。
しかしビジネスローンの場合、銀行でも3~5営業日もあれば審査結果が通知されます。
ノンバンクの中には即日融資してくれるところもあるほどです。
また審査が銀行融資と比較して甘めなのもおすすめです。
そもそもビジネスローンは銀行の融資が難しい中小企業向けの金融商品として開発されました。
ですから審査基準を銀行融資よりも低めに設定しているわけです。
ただし金利は高めなので注意しましょう。
ビジネスローンの金利を見てみると、1%台から14%程度といったところが相場です。
一方銀行融資の場合、1~4%が相場で中には1%を切るような利率で提供している商品もあります。
ですからつなぎ融資など、必要最小限の金額だけ借り入れるのがおすすめです。
黒字倒産に注意
中小企業の経営者の中には倒産と聞くと「赤字だったから倒産したのだろう」と思う人もいるかもしれません。
しかし黒字の状態でも倒産する事例は過去にいくらでもあります。
売り上げなどでみれば黒字でも、資金回収がなかなかうまくいかなければ資金繰りがうまくいかなくなります。
また黒字であることをいいことに多額設備投資をした結果、キャッシュフローがおかしくなって経営的に息詰まることも十分あり得ます。
資金が一時的に不足して、取引先への支払いができなくなる、給料の支払いが滞るなどで黒字でも倒産することは十分考えられます。
黒字だからといって、決して油断しないようにしてください。
もしかすると予定通りの資金回収ができなくなることも想定して、どう資金繰りでやりくりしていくかを検討しましょう。
中小企業の資金繰りのまとめ
中小企業の経営者や個人事業主の方は、資金が滞ってしまうと経営が厳しくなることを常に頭に入れておかないといけません。
黒字経営でも資金のサイクルが滞ると、倒産のリスクが出てきます。
ですからいざというときのことも視野に入れて、資金繰りをどうするか検討しなければなりません。
中小企業の利用できそうな資金繰りの方法は、ここで紹介したようにいろいろとあります。
金融機関など民間から借り入れる方法もあれば、公的な支援を受ける方法もあるでしょう。
自分たちの状況にマッチする方法で、資金調達を進めていきましょう。