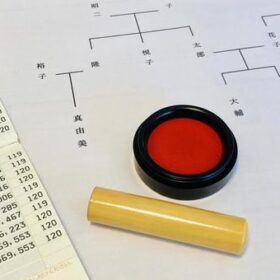診療報酬債権流動化は、短期間で現金化できるという大きなメリットがあります。医療機関にとっては、「診療報酬」を利用して現金化するという手法を使う事で、経営上の様々な課題をクリアできます。まずは、「債権流動化」という制度を簡単に紹介しましょう。
すぐに現金が欲しい状況というのは、どんな企業にもあるものです。「債権流動化」はそういった企業にとっては、短期間で現金を用意できる制度となっています。銀行の融資などでは煩雑な手続きがあり、審査にも時間がかかってしまします。一方で、「債権流動化」は優良債権さえあれば、それほど厳しくない審査で現金化ができ、国も推奨している制度であることはあまり知られていません。
実際に経済産業省は、資金調達の方法に「債権流動化」を推奨しています。政府は銀行融資に依存した企業経営から脱却する事を掲げており、その方策の一つが「債権流動化」なのです。債権を持っているのであれば、債権流動化を活用して企業系絵の効率化を目指しています。
問題は優良債権を用意できるのかです。こうした点において、病院はすぐに現金化できる債権を持っているという強みがあります。病院が用意できる優良債権というのが、「診療報酬」なのです。「診療報酬」は債権と見なすことができます。診療報酬債権という言葉は聞き馴染みがない人も多いので、その仕組みを見ていきましょう。
健康保険加入者が病院に行くと、窓口で支払いをします。例外的な場合を除き、窓口では医療費の3割を自己負担額として支払う事になります。そして、残りの7割は「診療報酬」として、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に請求することになるのです。この「診療報酬」は債権として見なされ、これを「診療報酬債権」と呼びます。
通常、診療報酬は月末までに金額を計算します。そして、翌月の10日までにレセプト(診療報酬明細書)を提出し、翌々月に診療報酬が振り込まれるという流れになります。しかし、医療機関によっては、医療従事者や事務員に給与を払う際に、現金が急遽必要になる場合もあります。そうした場合には、診療報酬の提出から振り込まれるまでのタイムラグがネックになるのです。その際に、現金を調達する方法が「診療報酬債権流動化」なのです。
「診療報酬債権」は、優良債権として知られています。通常、診療報酬の支払いが滞る事がなく、非常に信頼性の高い債権として審査会社に判断されるのです。医療機関は診療報酬債権を利用する事で、短期間で現金化することができます。その方法は様々ですが、銀行で融資を受ける場合よりも、短時間で現金化できる事が最大の魅力となっています。
様々な手法がとられる診療報酬債権流動化ですが、主に3つの方法があります。
・特別目的会社を設立する
・債権を信託銀行に信託する
・診療報酬債権ファクタリング
この3つの方法には、それぞれメリットとデメリットが存在します。「債権」というと「不良債権」などのネガティブなワードを連想する人もいると思います。しかし、この「債権流動化」は優良債権を使うため、資金に関するリスクはほとんどありません。特に、「診療報酬債権」は、国に準ずる信用機関の債権となるため、そうしたリスクはないとされています。そうした不安を払しょくするためにも、主に使用される3種類の方法を詳しく知っておくことが重要です。ますここでは仕組みについて簡単に説明し、次の章でメリットとデメリットを見ていきます。
まずは1つ目の特別目的会社を設立するという方法です。資金調達を目的とする会社を設立して、その会社に診療報酬債権を譲渡するという流れです。この場合には、特別目的会社が投資家に債権を売り、資金を調達します。集まった資金が医療機関にすぐに支払われ、その後、診療報酬は特別目的会社に支払われるという仕組みになっています。特別目的会社は、診療報酬から投資家に返金して取引は終了します。
2つ目は、信託銀行に診療報酬債権を信託します。信託銀行はその債権を投資家に売却して、その代金が医療機関に支払われます。その後、診療報酬は信託銀行に支払われるというのが、主な流れです。この2つの方法は投資家を経由する方法をとっています。そのため、融資を受けるほどではありませんが、ある程度の時間がかかるというのがポイントです。
こうしたことから診療報酬債権ファクタリングという方法が、選択される機会が増えています。利用する人も多いという事で、この診療報酬債権ファクタリングについては後述します。
ここでは診療報酬債権流動化のすべての手法に共通するメリット・デメリットを紹介していきましょう。手軽に現金化することができる「診療報酬債権流動化」ですが、もちろんメリット・デメリットが存在します。しっかりとメリットとデメリットをしておくことで、安全な資金管理ができるようになります。
診療報酬債権流動化のメリットを見ていきましょう。新型コロナウイルスの影響などで、医療機関が資金繰りに苦しむという話も聞こえてくるようになりました。診療報酬債権流動化は、そうした資金繰りに苦しむ病院にとっては非常に助かるメソッドとなっている。診療報酬債権流動化のメリットは主に3つ挙げることができます。
・資金確保が簡単になる
・審査が簡単に通る
・資産のオフバランス化ができる
診療報酬債権流動化の最大のメリットは、資金の確保が簡単になるという事です。通常は銀行などに融資などを頼めば、現金が手に入ります。しかし、これには時間もかかり、手続きも煩雑になる事が少なくありません。その一方で、診療報酬債権流動化はスピード感のあるやり取りが可能なので、現金化が短期間で行われます。
こうした事の背景には、2つ目のメリットである審査が簡単な事が関係しています。診療報酬というのは極めて信頼性が高い債権という事で、審査が簡単に通ります。仮に銀行融資が通りにくい場合でも、診療報酬債権であれば、審査を通すことが簡単な場合も多いのです。そのために、短期間での現金化が可能になるというメリットに繋がります。
3つめのメリットは資産のオフバランス化が可能になる事です。融資を受けると、それが負債として記載される事もあります。診療報酬債権流動化では、債権を現金化させただけなので負債にはなりません。
賃借対照表上では、売掛金の多さが効率的な事業ではないと判断されることもあり、診療報酬債権流動化はこうした事にもメリットをもたらします。債権を現金化すると売掛金が少なくなり、オフバランス化したことになるために経営の効率化が図れるのです。オフバランス化は企業価値を測る重要な指標であり、病院経営においても診療報酬債権流動化は大きなメリットとなります。
何事にもメリットがあればデメリットがあるものです。しかし、診療報酬債権流動化には、それほど大きなリスクは存在しません。それは診療報酬というものが、極めて優良な債権と見なされているからです。どの手法にも共通するデメリットと言えるのは、「手数料がかかる」ということです。
診療報酬額に対して、最低でも0.6%ほどの手数料がかかります。それほどの手数料ではありませんが、当然、通常の手順で診療報酬をもらうより受け取る金額が下がってしまいます。しかし、それ以上に大きなメリットがあるために、診療報酬債権流動化を行う医療機関が増えました。リスクが少なく、安心してできる資金調達法として「診療報酬債権流動化」は活用されています。
様々な手法がある中で最も手軽な方法が「診療報酬債権ファクタリング」です。「診療報酬債権ファクタリング」は、債権をファクタリング会社に売却する事で現金化する方法を指します。通常の債権流動化でも用いられる方法で、もちろん診療報酬債権流動化でも使用できる方法です。
一般的な流れでは、ファクタリング会社に債権を売却すると2回の支払いが発生します。1回目の支払いは診療報酬の約8割が支払われ、診療報酬が確定した後に手数料を差し引いた残額が支払われるという流れになります。
ファクタリング会社を使うメリットとしては、銀行の融資とは違い、担保がいらないという点が挙げられます。また、短期間での現金化が可能になり、初月の利用時には2か月分の債権を現金化する事ができる会社もあります。例えば、4月に初めてファクタリング会社を利用すると5月、6月の分の診療報酬債権を現金化することができるという事です。
診療報酬債権ファクタリングのデメリットは主に2つあります。
・途中で取引の停止ができない
・手数料がかかる
ファクタリング会社では通常、一度着手した流動化は途中でやめることができません。これは資金のショートを防ぐためで、ファクタリング会社にとってリスクを抑えるために、こうした契約内容になっている事がほとんどです。
もう1つは他の手法と同じく、手数料がかかるという事です。ファクタリング会社によって手数料は異なっていますが、「0.6%~」といった設定になっています。こうしたデメリットをしっかり理解したうえで、手続きが簡単な「診療報酬債権ファクタリング」を採用する医療機関が増えています。
短期間で現金が欲しいというのは、医療機関も抱えている悩みです。そうした悩みを解決する方法が「診療報酬債権流動化」となっています。メリットも多いですが、デメリットも確かに存在し、そうした事を理解することが資金繰りを安全に進めるためにも重要です。
優良債権をしっかりと活用するために、「診療報酬債権流動化」への知識を深める必要があります。短期間で現金化したい医療機関は、用途に合った流動化の手法を選択するといいでしょう。国も「債権流動化」については法改正を行っていて、推奨されている資金調達法です。今回の記事を参考にして、「診療報酬債権流動化」を資金マネジメントの選択肢の一つとして検討してみてください。