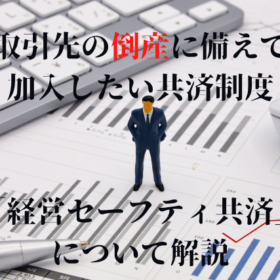助成金は、国、地方自治体、または民間団体が提供する支援金の事です。「特定の目的を達成する」という意味合いが強く、単純にビジネス目的の支援金ではない事も重要となっています。
返済の必要がない資金となっていて、適切な用途に利用される事が条件である事も少なくないので、しっかりと情報収集をする必要があるのです。この記事では助成金に関する最新動向や基本的な情報を解説していきましょう。
目次
助成金の全体像
助成金はしっかりと活用できれば事業を始めたり、継続したりする際には非常に有益です。銀行の融資やノンバンクのビジネスローンなどは、返済が大きな負担になってきます。さらに金利などの利子も大きなデメリットとなり、助成金はこうしたデメリットがない事が最大の特徴と言えるでしょう。ここでは助成金の全体像を解説するとともに、基本的な情報を紹介していきます。
助成金とは
助成金は銀行の融資などとは違って、返済の必要がありません。助成金は国、地方自治体、または民間団体が提供するという事で、ビジネスを軌道に乗せるためというよりは社会貢献や地域復興などの特定の目的に使用するという意味合いが強くなっています。
助成金はなぜ多用されるのか
受け取った金額を返済する必要がないという点や返済の負担を減らす事で事業に集中できるといった利点もあります。事業の成長を後押する目的の助成金もあり、様々な分野で助成金を利用する機会は増えています。
自己資金の節約もでき、他の事業運営費や将来的な投資にもその資金を当てられるようになります。社会的課題への貢献や企業の信用力向上など、助成金を利用すると事業を安定させる様々な効果があるのです。
銀行の融資では、返済をするだけでもかなり大変というイメージもあり、実際に月々の返済に追われている事業者も少なくありません。
こうした背景から返済の必要がなく、経営的な負担の少ない助成金をしっかりと活用する企業が増えてきています。
注目すべき助成金分野
助成金は給付対象になっていないと利用できません。近年では助成金は多くの団体が提供していますが、社会の変化と共に注目されている助成金分野を紹介してきましょう。
以下の分野では特に多くの助成金制度が提供されています。
・環境対策
・デジタル化支援
・地域活性化
注目すべき助成金分野・環境対策
環境対策は、環境保全や脱炭素化に向けた取り組みを支援するという目的です。例えば、省エネ設備の導入支援や再生可能エネルギーの普及をするための助成金が、これに当たります。環境に関する意識は年々強まっていて、SGDsなどの取り組みがこうした助成金に繋がっています。
注目すべき助成金分野・デジタル化支援
デジタル化支援とは、2020年代に特に活発になっている助成金の分野です。デジタルトランスフォーメーション(DX)が近年では大きな関心事であり、企業もこうした取り組みを積極的に行っています。国などもこうした考えを積極的に後押ししており、企業の業務効率化やデジタルトランスフォーメーション(DX)を促進するためという目的で助成金が数多く提供されていて、様々な企業が活用しています。ITツール導入やサイバーセキュリティ強化などに利用でき、顧客にとっても有益なサービスに使用できます。
注目すべき助成金分野・地域活性化
地域活性化はさらに広い分野に活用できる助成金です。地域経済の活性化や雇用創出などを目的としていて、国も積極的に助成金を児提供している分野です。過疎地域や地方都市での事業活動を支援するという事で、地方自治体にもこうした助成金があります。
国・地方自治体・民間の助成金の違い
国・地方自治体・民間の助成金の違いも知っておきましょう。助成金と言えば、「国や自治体が提供する」というイメージも強いと思います。国が提供する助成金は、全国規模での課題解決や政策目標達成などを目的にしています。金額も高額になる傾向にあり、申請要件が厳しいという特性があります。競争率が高く、助成金の対象になっていても、選ばれないという可能性もある狭き門となる助成金となっています。
より身近なのが、地方自治体の助成金です。地方自治体が提供する助成金の特徴は、地域特有の課題やニーズに対応するというモノです。ネックとしては申請対象が地域内に限定されるという事で、そのエリアにいる事が必須対象となっています。国の助成金とは違ってエリア内の事業者であれば、比較的採択されやすい助成金となっています。
民間の助成金も近年では増えてきています。民間企業や財団が提供する助成金という事で、特定の分野や目的に焦点を当てていて、金額も幅広く提供されています。特徴としては柔軟性があるという点です。しかし、民間団体や企業が提供しているという事で、募集が不定期であるという場合も少なくありません。
こうした違いを理解する事は、効率よく助成金を使用するには必須です。そのため、どの団体が提供していて、メリットとデメリットは何かといった情報収集が重要で、自分の事業にあった助成金には常にアンテナを張っておく必要があります。
助成金最新トレンドとは?
助成金最新トレンドは押さえておくと安心して利用できます。金融機関などでは、金利の変動などの影響を大きく受けてしまい、事業にも様々寧興が出てしまう可能性もあります。助成金であれば、返済リスクもなく、最新のトレンドを抑えていれば、積極的に活動ができます。ここではデジタル化、中小企業支援、人材育成、働き方改革といった最新のトレンドを簡単にまとめていきましょう。
中小企業のDX推進を支える助成金
中小企業のDX推進を支える助成金は、最も注目されている分野です。先述したDX推進を支える助成金をもう少し詳しく紹介しましょう。企業が競争力を維持し、業務効率を向上させることを目的として、DXは国を挙げて推進されています。具体的には、ITツール導入補助が挙げられます。会計ソフトや顧客管理システム(CRM)、在庫管理システムなどがそれにあたります。
AI・IoT活用支援も助成金があり、近年急速に発展している人工知能(AI)や定着しつつあるインターネット(IoT)技術の導入などが、企業の活用例となっています。
さらに、ランサムウェアや情報流出などが社会問題化しているために、サイバーセキュリティ強化も急務です。そのため、デジタル化に伴うセキュリティリスクへの対策費用を支援する制度も数多く準備されています。
人材育成や働き方改革を目的とした支援策
人材育成や働き方改革を目的とした支援策も、人手不足問題などで注目されている助成金です。社会の多様化や労働環境の変化に対応するという事は国の方針となっているのです。こうした事情から企業の人材育成や働き方改革を支援するための助成金は、数多く集まっています。
さらに、これに関連してスキルアップ支援なども注目されている助成金です。従業員の能力開発や専門スキルの習得を支援するリスキリングなどを支援する事にも助成金を出しています。リスキリングの資格取得や職業訓練にかかる費用の一部を補助すると言った補助金が、国だけでなく、民間企業でも提供している例があります。
新型コロナウイルス流行後にはテレワーク推進などにも助成金が提供されています。リモートワーク環境整備に関する助成金などもあり、急増する需要に対応するためにこうした分野の助成金も数多く準備されているのです
助成金を活用するメリットと注意点
ここでは、助成金を活用するメリットと注意点を見ていきましょう。助成金には、企業や団体にとって大きな助けとなるというメリットがある事は解説してきました。こうした助成金を利用する際にはいくつかの注意点もあります。ここでは、助成金の利点とともに、申請や運用でのリスクについて注意すべきポイントを紹介していきます。
資金調達の負担を軽減する助成金の利点
助成金を活用することで、利用者側が受容する利点には以下のモノが考えられます。
返済不要の資金調達
成長分野への挑戦を支援
経営リスクの低減
返済不要の資金調達と点は最大のメリットとなります。助成金は融資とは違い、返済義務がありません。返済や金利は資金調達の負担となるために、助成金はこうした点で大きなメリットを持っています。特に資金がそれほど潤沢でない新規事業や初期投資を行う際には、非常に有益となっています。
成長分野への挑戦は、事業を拡大する際には避けては通れません。そんな企業のためにも支援環境対策やデジタル化など成長が期待される分野では、助成金を受ける事ができます。助成金を活用する事によって、資金的な負担がなく、挑戦する事ができるというメリットが生まれるのです。
経営リスクの低減は、大きなメリットです。助成金により自己資金の消耗を抑えるという効果が生まれ、資金繰りが安定します。資金繰りが安定していると、新たな融資を受ける事もできます。さらに、経営の安定性が向上する事によって、投資の対象として高評価を受けるでしょう。こうした好循環を生む効果が助成金にはあるという事は知っておくといいです。
審査や申請における落とし穴
審査や申請における落とし穴も知っておきましょう。銀行の融資などとは違い、返済がないという利点は大きいですが、デメリットもしっかりと知っておかないと思わぬ落とし穴にはまってしまいます。特に、助成金の申請には、落とし穴が多く、デメリットが多いともいわれています。
主に注意しなければいけないのは、以下のような注意点です。
・申請書類の煩雑さ
・競争率の高さ
・不採択のリスク
助成金申請には詳細な事業計画書や収支見込書の作成が必要です。これには、時間と労力がかかり、場合によってはメガバンクの審査以上の準備が必要となります。さらに、競争率の高さは大きな問題となっていて、人気の助成金は審査が厳しくなる傾向があります。
無事に提出を終えても、不採択のリスクがあり、費やした労力が無駄になるという事は覚悟しておきましょう。国の助成金ではこうした傾向が強まり、「準備に奔走した挙句、助成金は支給されなかった」という例も少なくありません。
遵守事項と返還リスク
遵守事項と返還リスクなどもしっかりと知っておく必要があります。助成金を受け取った後にも、遵守すべき事項があり、こうした点はノンバンクのビジネスローンなどとは一線を画します。
これらを怠ると、助成金の返還を求められるというリスクがあり、これを返還リスクと呼びます。目的外使用の禁止や報告義務など、助成金の活用ルールは把握してかなければならないのです。
メリットを最大限に引き出しつつ、リスクを最小限に抑えるように情報収集と助成金管理には注意深く取り組まなければなりません。
国の助成金は審査がとにかく大変
国の助成金は審査基準が厳格であり、民間の助成金とは比べ物にならないほどのハードルが存在します。国の助成金は国民の税金が財源となっている事もあり、その用途なども厳格に制限されているのです。
助成金には明確な目的が設定されている事も少なくありません。その目的としては以下のモノが重視されています。
・社会的意義(どのような課題を解決するのか)
・実現可能性(計画が実行可能であるか)
・持続性(助成金終了後も事業が継続するか)
といった三点は特に重要視され、社会全体にとって利益がなければ助成金としての意義はないとみなされます。
助成金に選ばれた後にも、報告義務があります。他の助成金も報告義務はありますが、国の助成金はかなり厳しいチェックが入ります。定期的な進捗報告や成果報告が求められ、この報告が不適切だと、助成金の返還を求められるという例も少なくありません。
国の助成金は大企業であっても助成金を容易には許可が出ないので、中小企業などの場合は入念な準備が必要な事は知っておきましょう。
助成金のまとめ
助成金は事業を継続する際にも非常に有益です。様々な社会課題の解決にも利用され、変化する経済環境や社会課題に対応する事ができます。持続的な成長を目指すためにも、返済が不要な助成金を活用しない手はありません。
助成金の最新トレンドを把握すると助成金のメリットを最大限に利用することができるため、この記事の情報も参考して助成金を利用するといいでしょう。