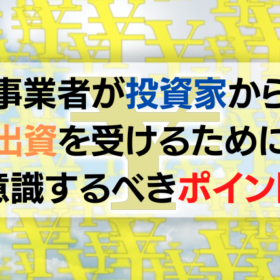「資金繰り」と日常普通に使っていますが、その意味はご存知ですか?会社の運営に資金繰りが欠かせないことは、経営者なら当然わかっているでしょう。
ではどうやって経営が安定するような資金繰りができるのか?
それを知るには、そもそも資金繰りについてしっかりと理解を深める必要があります。
そこで今回は資金繰りの基本事項から、会社の資金繰りを改善するポイントまで銀行員が解説します。
現場で融資審査している銀行員の説明なので、会社の資金繰りを改善したい人や、資金調達を考えている人は是非参考にしてください。
実際に銀行で私が担当する企業の経営者にアドバイスしていることを中心に説明します。銀行員のアドバイス(指示、命令ととるかはおまかせします)として参考にしてください。
<会社資金繰り改善・3つのポイント>
1. 収入(売上や利益)
2. 支出(支払い)
3. 資金調達(新規融資や返済見直し)
会社資金繰り改善のポイント1.収入(売上や利益)
まず売上などお金が入ってくる収入面から始めましょう。
販売先の見直し
なによりも、売上が不振なら販売先の見直しが最優先事項です。
もちろん自社の商品やサービスに問題があれば別ですが、自社に問題がないなら売上が伸びないのは、販売する相手に問題があるということになります。
銀行で融資を受けている場合、毎年の決算書や試算表などを定期的に提出する必要がありますが、そうして提出した決算内容を見て、銀行員は「売上が不振なら売り先(販売対象)を見直せ」と言ってきます。
もちろん銀行員に言われるまでもなく、販売先の見直しは常にやっているはずです。
しかし中には「親の代から世話になって、取引を切ることはできない」といった理由でズルズルと取引を続け、結局自社の業績悪化が進むだけという会社もあるのです。
しかしそういった事情でも「銀行にきびしく言われて、断腸の思いで取引をやめることに決めた」と言えば相手も強くは言えないでしょう。
これは実際、私がお客様の会社の資金繰り改善の相談を受け、販売先を見直すためにアドバイスしたことです。(実際にそのセリフを使ったかわかりませんが、販売先の見直しができました)
利幅(採算性)を考える
これも売上につながる話ですが、販売やサービスの供与では、そのために費やした費用(原価)に見合う利益があるのか?つまり費用対効果と採算性を考える必要があります。
したがって採算性が低い、あるいは採算が取れない(売れば売るほど赤字になる)ような取引は思い切って断ち切る決断が必要な場合もあります。
これも当然といえば当然で、経営者なら誰でも考えるはずです。
しかし中にはこうした意識がうすい会社もあるのです。
これは私が担当していた建設業の会社ですが、とにかく頼まれればどんどん仕事を受ける社長さんがいました。
創業以来ずっとこの方針を貫き「ウチの会社は人がやらない仕事でもなんでもやる。なぜならそれは人助けだから、次の仕事にもつながる」と考えている社長さんでした。
勢いがあった時代に相当設けたそうで、自宅や車も高級なものばかりでした。
しかし景気が悪くなり始めると仕事の数が減って奪い合いになり、もともと請け負う仕事の採算など考えない「どんぶり勘定」だったので、結局見積もりで負け仕事が取れなくなり、この社長でも「やればやるほど赤字」とわかるような仕事しか回って来なくなりました。
それでも支払いや社員の給料を払うために赤字覚悟で仕事を続け、業績は悪化するばかりだったので、廃業も考えるべきとお話をしたのですが(銀行は、相手のためになると判断すれば廃業を検討するようアドバイスすることもあります)最後には破綻してしまいました。
会社資金繰り改善のポイント2.支出(支払いや借入返済)
会社資金繰り改善で、2つ目のポイントは支出、つまり出ていくお金の改善です。
業務の「カイゼン」
支出面では業務の見直しが有効な手段です。
なぜならこれまで続けてきたプロセスを見直したり廃止したりすれば、経費の節約につながることもあるからです。
もちろんこれも教科書的な考えかもしれません。
しかし漫然とルーティンを繰り返し、業務の見直しなど一切考えてこなかった会社もあり、私もそういった会社が破綻した例を何度も経験してきました。
たとえば有名なトヨタの「カイゼン」という概念があります。
そもそも改善とは悪いところを良くするという意味です。
しかし世界に冠たるトヨタに悪いところなど無いはずですが、それでも「現状に満足せず、もっと良くできないか?まだ見直すところはあるはず!」という課題意識からあえてカタカナの「カイゼン」と呼び、経営者だけでなく現場の従業員でもアイデアや意見を自由に言える社風があるそうです。
いっぽうこれも私が担当していた観光旅館ですが、創業からのしきたりや習慣を一切変えようとしない社長がいました。
「老舗としてのプライド」と社長はおっしゃいましたが、そのために業績が不審になるなら、それはもはや「悪習」だと考えた私は、見直しや改善を求めたのですが聞き入れてもらえませんでした。
そして私の「苦言」をイヤだと感じて他の金融機関に移って行きましたが、結局は破綻という結末になってしまいました。(銀行員として「ざまあみろ」などとは思えず、力になれなかったという気持ちだけが残りました)
固定費の徹底的な見直し
事務所の家賃から水道光熱費などの固定費も見直しが必要です。
固定費は、文字通り固定しているからこそ「固定費」と呼ばれるわけですが、見直しにより金額は固定どころか削減できる余地は意外と残っているものです。
「自社では徹底的に固定費を見直し済みで、これ以上はどこにも余地はない」とおっしゃる社長さんがいましたが、それでも見直しはしたいという気持ちもある人だったので、コンサルタント会社を紹介しました。
その結果「徹底的に固定費を見直したつもりでいたが、徹底していなかった。おかげで経費の削減ができた、ありがとう」とお言葉をいただきました。
このように、自分達当事者だけでは以上見直す余地が見つからない場合などは、コンサルティング関連の会社に相談してみるのも一考です。(銀行では顧客の経営支援策として、相手にメリットのある事業者を紹介しています。「マッチング」などと呼び、取引企業とのリレーション強化の一環なので無料で紹介してもらえるので、機会があれば銀行員に相談することをおすすめします)
会社資金繰り改善のポイント3.資金調達(新規融資や返済見直し))
3つ目で最後になる会社資金繰り改善のポイントは「資金調達」で、融資や返済について見てみましょう。
新規融資のときに考えるべきこと
融資取引をしている銀行で資金調達しようと新規融資を受けるときは、会社資金繰りを考えて銀行に確認する、あるいは交渉することも必要です。
たとえば借入希望額や使いみちなどは聞かれても、返済方法や金利などは銀行から言われるままに借りるというのが一般的な流れでしょう。
しかしこのとき「なぜ今回はこの金利なのか?前回より高くなっているが、その理由は?」などと聞いてみるのも有効です。
これは文句を言っているわけではなく、融資取引する顧客としてその内容を確認するのは当然の權利だからです。
もちろん言葉使いや口調も工夫して、もめないようにスマートに聞く方がいいでしょうが、そうすれば銀行員はどうして今回の条件になったのか説明してくれるはずです。
それとは逆に、説明など無く「嫌ならよそで借りれば?」といったような言動なら、その銀行の方針もわかるので、今後の付き合い自体を考え直す必要があるかも知れません。
社長さんの中にはよく「◯◯銀行には困ったときに助けてもらったので足を向けて寝られない」などと言ってくださる人もいますが、銀行は仕事として融資しただけで、あなたがどれだけ感謝していても、業績悪化になれば今度も仕事として冷静に手を引くだけです。
返済中の融資を一本化する
事業資金融資を何回か借りていると、当然ながら借り入れの本数も増えてきます。
現在、複数の返済があるなら返済中の融資をまとめて一本化すると会社の資金繰りが安定する可能性があります。
それは、同じ借り入れでも複数になるほど資金繰りが大変になるからです。
これは例で見てみましょう
<例1>3千万円の返済・複数明細と一口で返済する場合の比較
前提条件:借入金額3千万円、返済回数60回(シンプルにするため金利は含めない)
【一口】 毎回返済額計:50万円(3千万円÷60回)
【複数明細】毎回返済額計:50万円(A〜C)
A・借入金額1千万円 ⇒毎回返済額:16万7千円
B・借入金額1千5百万円⇒毎回返済額:25万円
C・借入金額5百万円 ⇒毎回返済額:8万3千円
借りる金額が同じなので、毎回返済元金も同じですが、複数明細の返済日がそれぞれ異なっていたら、その都度返済日と資金繰りを考えなければいけません。
家計の口座なら給料日のあとで、ローンやクレジットなど支払いに必要なお金をまとめて入金しておくこともできます。
しかしこれが会社の事業資金なら、余分なお金を口座に置いておくのは合理的ではありません。
そこで、複数明細を一本化すれば資金繰りもしやすくなるのです。
返済中融資を一本化したり、新規融資を受けるときに返済中融資も一緒にまとめる「借り換え」をしたりと、方法はいくつかありますので、取引している銀行に相談してみると良いでしょう。
たとえば私の場合、新規融資の相談があれば、まず返済中融資とまとめられないか?を考えます。
そしてまとめられる借り入れがあれば一本化して、会社の資金繰りが複雑にならないよう意識しています。
いっぽう金融機関や担当者によっては、申し込みがあればどんどん新規融資を追加し、単純に融資実行日をそのまま返済日にして結局返済日がバラバラとなり会社資金繰りが大変になっているケースもあります。
顧客の会社資金繰りに配慮しているなら、金融機関は頼まれなくても一本化や新規融資での借り換えを考えるべきですし、まして返済日もバラバラで会社資金繰りを考慮してくれないなら、その金融機関との取引は考え直したほうがいいかも知れません。
他行への肩代わり
上記にも通じますが、取引している金融機関の金利が高い、あるいは自社に対する姿勢などに満足できない場合には、他の金融機関に全面肩代わりすれば、借入金利が下がるなど会社資金繰りが安定化する可能性があります。
ただし、一度全面肩代わりをして他の金融機関に移ったなら、元の金融機関で再び融資を受けるのは不可能になるので、その覚悟が必要になります。
なぜなら、事業資金融資というのも一つの契約であって、5年返済なら5年間分割して返済するという約束を金融機関との間で交わしたとも言えるのです。
それを、会社の資金繰りのためと言っても、自分から契約破棄したわけなので「もうそちら(もとの金融機関)とは取引しない」と決別を宣言したことになり、あとになって会社資金繰りが苦しくなったからと言って元の銀行に融資を申し込んでも取引を再開することはできないでしょう。
肩代わりをして取引を解消された顧客は、その金融機関から見ても取引すべき相手ではないと判断しますので、あとから再び融資の申し込みがあっても融資はむずかしいでしょう。
「昔のよしみでぜひお取引の再開を!」などと言うことはまず無いと考えるべきです。(一度去った顧客とは二度と取引しない、金融機関としてのプライドも多少はあります)
おすすめのビジネスローン会社比較表
それぞれの会社には独自の特徴がありますが、なかには審査を受けるハードルが比較的低く、スピーディーな融資に対応しているところもあります。特に、代表者が金融ブラックでも借入が可能なケースや、保証人・担保なしで申し込める商品もあります。
法人がビジネスローンを利用する時には、資金不足や支払い遅延による倒産のリスク、いわゆる黒字倒産を防ぐために、返済計画をしっかり作成し、資金繰りやキャッシュフローの状態を正確に把握・管理することが重要です。融資を受けるだけでなく、補助金や助成金の制度も活用すれば、財務基盤の強化や事業資産の増加にもつながります。
また、事業を続ける上では収支のバランスを毎月チェックし、人件費や設備費などの出金タイミングを調整することが求められます。必要に応じて、税理士や財務の専門家に相談して、損益計算書や収益、支払項目の状況を整理した資料を作成することも役立ちます。
例えば、在庫の売却や不要な購入の見直しを行うことで、手元に残る金を確保し、短期的な資金不足の影響を抑えることが可能です。事業活動や営業活動の中で発生する支出の増減を把握し、未来の支払いリスクを予測しながら、計画的に投資や事業の継続に必要な資金を動かすことが重要です。
ここで紹介したように、会社経営における資金管理は単なる融資利用に留まらず、制度活用やコラムでの情報収集、過去の事例分析など、幅広い方法で行うことができます。適切な管理を行い、リスクを回避しながら事業の安定した成長を目指しましょう。
| 業者名 | 融資対象 | 金利 | 入金スピード | 融資限度額 |
|---|---|---|---|---|
| アクトウィル | 法人 | 7.5%~15% | 最短即日 | 最大1億円 |
| AGビジネスサポート | 法人・個人事業主 | 3.1%~18% | 最短即日 | 1000万円 |
| ファンドワン | 法人 | 2.5%~18% | 最短即日 | 1億円 |
| デイリーキャッシング | 法人・個人 | 5.2%~18% | 最短即日 | 8000万円 |
| 株式会社オージェイ | 法人・個人 | 9.5%~18% | 最短即日 | 1億円 |
| Carent | 法人 | 7.8%~15% | 最短即日 | 500万円 |
| オリックス・クレジット | 法人・個人 | 6.0%〜17.8% | 最短即日 | 500万円 |
| ビジネスパートナー | 法人・個人 | 9.98%〜18.0% | 最短5日 | 500万円 |
| いつも | 法人・個人 | 4.8%~18.0% | 最短即日 | 500万円 |
| プロミス | 個人 | 6.3%~17.8% | 最短即日 | 300万円 |
| GMOあおぞらネット銀行「あんしんワイド」 | 法人 | 0.9%~14.0% | 最短2営業日 | 最大1,000万円 |
おすすめのビジネスローン会社概要
アクトウィル

アクトウィル株式会社は、法人向けの事業者金融です。申込は電話かメールでメールだと24時間受付しています。
必要書類はFAXで提出でき、最短即日で審査可能です。アクトウィルは低金利と大口融資が可能で、実質年率7.5%~15%と比較的低い金利で融資が受けられます。また、最大1億円の融資が受けられるため、まとまった資金の調達をしたい企業におすすめです。融資は法人契約の為ため、代表者の連帯保証のみで第三者による保証人や不動産担保は不要です。メールでの相談やお問い合わせは24時間受付してますので、営業時間外でも問い合わせられます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 7.5%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | アクトウィル株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31521号 |
| 住所 | 〒160-0022 東京都豊島区東池袋3-11-9 |
| 電話番号 | 03-5944-9168 |
| FAX番号 | 03-5944-9169 |
| 営業時間 | 平日9:00~20:00 |
AGビジネスサポート

AGビジネスサポートは、企業の成長を支援するためのビジネスローンを提供しています。AGビジネスサポートのビジネスローンは、資金調達のニーズに応じて柔軟に対応し、迅速な審査と融資を実現します。特に、中小企業やスタートアップ企業にとって、資金繰りは重要な課題です。AGビジネスサポートでは、経営者の皆様が抱える資金の悩みを解消し、事業の発展をサポートすることを使命としています。
AGビジネスサポートのビジネスローンは、用途に応じた多様なプランを用意しており、設備投資や運転資金、さらには新規事業の立ち上げ資金など、さまざまなニーズに対応可能です。審査基準も柔軟で、過去の実績や信用情報だけでなく、将来のビジョンや事業計画を重視した評価を行います。これにより、資金調達が難しいとされる企業でも、安心してご相談いただけます。さらに、AGビジネスサポートでは、専門のスタッフが個別にサポートを行い、最適なプランをご提案します。お客様のビジネスの特性や成長段階に応じたアドバイスを行い、資金調達のプロセスをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1000万円 |
| 金利 | 3.1%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | AGビジネスサポート株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01262号 日本貸金業協会会員第001208号 |
| 住所 | 東京都港区芝2丁目31-19 |
| 電話番号 | 0120-027-120 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 平日9:30~18:00 |
ファンドワン

ファンドワン株式会社は、東京都豊島区南大塚に本社を構える、事業者向け金融サービスを提供する企業です。2020年1月に設立され、資本金5,000万円を基盤に事業を展開しています。同社は、全国の事業主に対し、迅速かつ柔軟な与信判断と安心の金利帯で資金調達を支援しています。
提供するサービスには、無担保の事業者ローンや、不動産・売掛債権を担保としたローン、車担保融資、介護・診療報酬担保融資など、多様な商品が含まれています。最短40分のスピード審査や、最大1億円の大型融資が可能である点が特長で、赤字決算や税金・社会保険料に課題を抱える事業主にも柔軟に対応しています。
ファンドワン株式会社は、単なる資金提供に留まらず、中小企業の成長を支援し、地域社会や日本経済全体の活性化に貢献することを使命としています。これまで、経営難に直面した多くの企業の資金繰りや経営再建をサポートしてきました。同社は、経験豊富なスタッフが最適なプランを提案し、事業主とともに成長を目指すパートナーとして信頼されています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 2.5%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | ファンドワン株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(2)第31816号 |
| 住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚二丁目39-11 ヒサビル6階 |
| 電話番号 | 03-5395-8888 |
| FAX番号 | 03-5395-8800 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
デイリーキャッシング

株式会社デイリープランニングは、個人のお客様から法人のお客様まで幅広いニーズに対応したローンサービスを提供している企業です。主に「フリーローン」「おまとめローン」「不動産担保ローン」「ビジネスローン」を取り扱い、それぞれの状況に最適な融資プランを提案しています。
同社のサービスは、全国どこからでも利用可能で、急な資金需要に柔軟に対応します。特に、急な出費や資金繰りの困難を抱える方々に、迅速かつ確実な融資の手続きを提供し、お客様の生活やビジネスを支えています。
さらに、デイリープランニングでは、融資の申し込みが簡単で、インターネットや電話、店舗での手続きもスムーズ。お客様一人ひとりの状況に合わせた親身な対応を心掛け、信頼性の高いサービスを提供しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 8000万円 |
| 金利 | 5.2%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社デイリープランニング |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(3)第31698号 |
| 住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-12徳永ビル4階401号 |
| 電話番号 | 03-6284-3674 |
| FAX番号 | 03-6284-3675 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
株式会社オージェイ

株式会社オージェイは、法人向けに多彩な融資サービスを提供する企業で、事業資金の調達をサポートします。提供する融資メニューには、無担保融資、手形割引融資、不動産担保融資、動産担保融資、ファクタリング、診療報酬担保融資などがあり、さまざまな事業ニーズに柔軟に対応しています。
同社は、急な資金調達が求められる場面でも迅速に対応できる体制を整えており、審査もスピーディで信頼性の高いサービスを提供しています。また、日本貸金業協会に加盟しており、法的にも安心して利用できることが保障されています。中小企業や個人事業主など、資金繰りに困っている事業者に対して、親身なサポートを行い、ビジネスの安定と成長を支援しています
さらに、オンラインで簡単に申し込めるため、全国どこからでも迅速で効率的な資金調達が可能です。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 9.5%~18% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社オージェイ |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31549号 |
| 住所 | 東京都中野区中央1-32-5 青光堂ビル3F |
| 電話番号 | 03-5332-3833 |
| FAX番号 | 03-5322-3834 |
| 営業時間 | 平日10:00~15:00 |
Carent

事業資金のニーズに柔軟に応える「Carent ビジネスローン」は、スピーディーで安心の融資サービスです。中小企業や個人事業主の方々が直面する資金繰りの課題を解決し、成長をサポートします。
柔軟な条件設定:事業規模や状況に合わせた融資プランをご提案。迅速な審査:最短○日で審査完了、資金調達をスムーズに。安心のサポート体制:専門スタッフがご相談から契約まで親身に対応します。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 7.8%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社IPGファイナンシャルソリューションズ(キャレント) |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(5) 第31399号 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-24-4 WEST HILLビル5階 |
| 電話番号 | 03-5740-5087 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 |
オリックス・クレジット

オリックス・クレジット株式会社は、1979年にオリックス株式会社とフランスの大手信販会社セテレム社の合弁により設立され、オリックスグループ初の個人向け金融サービスを提供する企業として誕生しました。設立当初はショッピングクレジットや有担保ローンを中心に展開していましたが、1987年には低金利かつ高額融資が可能な「VIPローンカード」を発売し、プレミアム・カードローン市場の先駆者としての地位を築きました。
その後、貸金業法の改正に伴い、市場環境の変化に対応するため、これまで培った与信やオペレーションのノウハウを活かし、金融機関向けの信用保証事業に注力。現在では全国250社以上の金融機関と提携し、同社の主力事業の一つとなっています。
さらに、オリックス株式会社から事業を継承し、モーゲージバンク事業にも参入。「フラット35」を中心とした住宅ローン商品を提供し、新築だけでなく中古物件のリノベーション向けや地域活性化と連携した商品など、多様なニーズに応じたサービスを展開しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 6.0%〜17.8% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00170号 |
| 住所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー |
| 電話番号 | 非公開 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
ビジネスパートナー
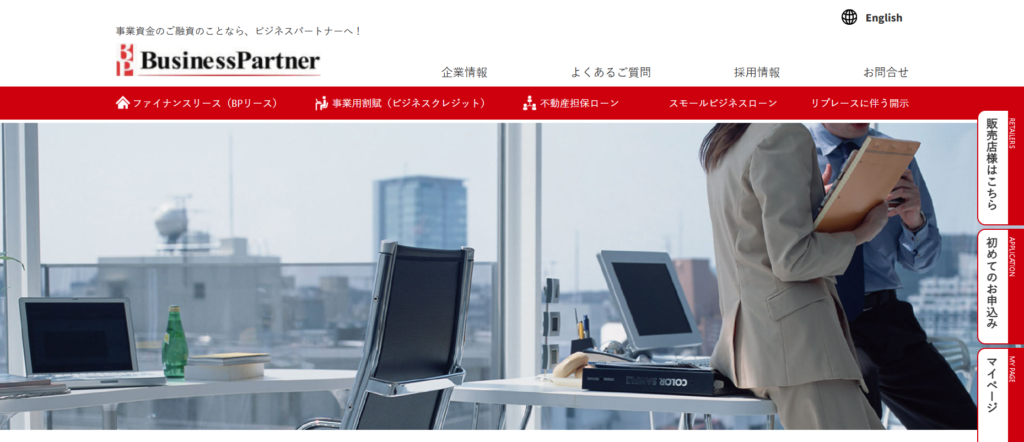
株式会社ビジネスパートナーは、1999年に設立され、東京都新宿区に本社を構える金融サービス企業です。中小企業や個人事業主向けに、柔軟な事業資金融資を提供しており、特にスピーディーな資金調達を求める事業者に支持されています。
同社の主力商品である「スモールビジネスローン」は、来店不要で契約可能な無担保ローンで、事業資金の用途に応じた自由な活用が可能です。原則として担保や保証人を必要とせず、手数料もかからないため、資金調達のハードルが低いのが特長です。また、セブン銀行ATMを活用することで、365日24時間、資金の引き出しや返済が可能な利便性の高いサービスを提供しています。
さらに、ファイナンスリース「BPリース」や事業用割賦「ビジネスクレジット」、不動産担保ローンなど、多様な資金調達の選択肢を用意。事業運営に必要な資金を柔軟に確保できるよう支援し、企業の成長をサポートしています。特に、事務処理の簡素化や全額損金処理の可能性など、経営効率を向上させるメリットも提供しています。
ビジネスパートナーは、迅速かつ柔軟な資金提供を通じて、中小企業の発展を支える信頼できる金融パートナーとして、多くの事業者に利用されています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 9.98%〜18.0% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短5日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社ビジネスパートナー |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01500号 |
| 住所 | 〒160−0022 東京都新宿区新宿6‐27−56 新宿スクエア6F |
| 電話番号 | 非公開 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
いつも
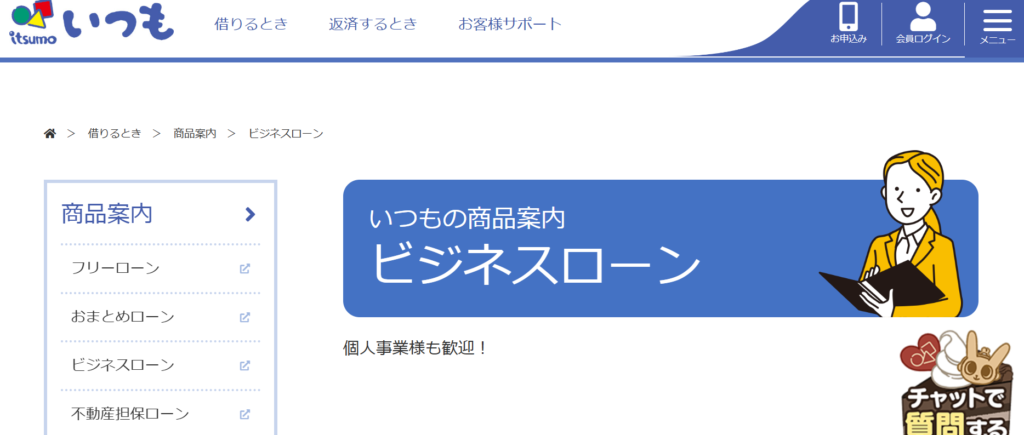
株式会社K・ライズホールディングス(ブランド名:いつも -itsumo-) は、個人および法人向けに多様なローンサービスを提供する金融会社です。主な取り扱い商品には、フリーローン、おまとめローン、ビジネスローン、不動産担保ローンなどがあります。
特に ビジネスローン は、個人事業主や法人の事業資金ニーズに対応し、迅速かつ柔軟な融資を実施。オンラインでの申し込みは 24時間365日対応可能 で、最短30分での審査・融資も可能です。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円 |
| 金利 | 4.8%~18.0% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社K・ライズホールディングス |
|---|---|
| 登録番号 | 高知県知事(4)第01519号 日本貸金業協会会員 第005847号 |
| 住所 | 高知県高知市杉井流5-18 |
| 電話番号 | 0570-055-126 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 不明 |
プロミス

個人事業主の資金調達をサポート!プロミス「自営者カードローン」は事業を運営する上で、急な資金ニーズ に対応できる柔軟なローンがあると心強いものです。プロミスの「自営者カードローン」は、個人事業主の方を対象 としたローンサービスで、最大300万円 まで借入可能。事業資金だけでなく、プライベートな用途 にも利用できるため、事業と個人の資金管理をスムーズに行えます。
申し込みは 24時間365日 受け付けており、インターネットから簡単に手続き可能。さらに、スピーディーな審査と融資 により、急な資金調達にも対応できるのが大きな魅力です。例えば、運転資金や設備投資、仕入れ資金 など、さまざまな用途で活用できます。また、必要書類も本人確認書類 と 事業内容を確認できる書類(例:確定申告書) のみとシンプル。手続きが簡単で、事業を営む方の負担を最小限に抑えられます。。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 300万円 |
| 金利 | 6.3%~17.8% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00615号 |
| 住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル |
| 電話番号 | (03)6887-1515 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 不明 |
GMOあおぞらネット銀行「あんしんワイド」

法人の資金繰りをサポートするGMOあおぞらネット銀行のビジネスローン「あんしんワイド」は、事業資金の幅広いニーズに対応できる柔軟なローンサービスです。最大1,000万円まで借入可能で、設備投資や運転資金、仕入れ資金など、さまざまな用途に活用できます。
申し込みはオンラインで完結し、必要書類も少なくスピーディー。最短2営業日での審査・融資に対応しており、急な資金需要にも頼れるのが特徴です。担保や保証人は不要で、全国の法人が対象となっています。
| 区分 | 銀行 |
|---|---|
| 融資限度額 | 1,000万円 |
| 金利 | 0.9%~14.0% |
| 審査日数 | 最短2営業日 |
| 入金スピード | 最短2営業日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第321号 |
| 住所 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
| 電話番号 | 03-3461-5000 |
| FAX番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:00(オンラインは24時間受付) |
会社資金繰り改善のポイントを銀行員が解説します〜まとめ
全面肩代わりのように、会社資金繰りを改善するための方策にも、相手がある場合には配慮や注意が必要になります。
たとえばこの記事で紹介した以外にも、売掛金のサイト短縮(売掛入金が3か月後の販売先と交渉して、2ヶ月後の回収にしてもらう・収入の改善)とか、逆に買掛金サイトの延長(仕入れ代金の買掛金支払い期限は3ヶ月後だが、交渉して支払い期限を6ヶ月に延長してもらう・支出の改善)なども考えられます。
しかしこれらはすべて販売先、仕入先など相手があり、その相手にも資金繰りがあるわけです。
会社経営を続ける上で資金繰りが苦しい局面は、会社設立直後や事業拡大期などにも訪れます。そうしたときには、交渉の際に相手との関係を損なわないため、条件変更の依頼内容を表などで整理して提示したり、資金繰り改善を支援する会計ソフトを活用したりするのも有効です。
会社資金繰りを改善するにも、相手があれば実現できないこともあるでしょうし、強行すれば反感を買い、最終的に取引が無くなってしまったなら本末転倒になりかねませんので、ここは慎重に考える必要があります。
この記事が会社資金繰り改善の参考になれば幸いです。