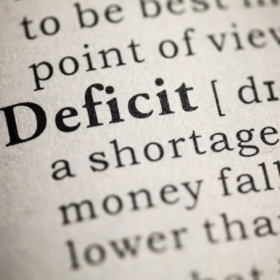「後払い現金化」やSNSを悪用した「個人間融資」など、多種多様な手口を用いた悪徳金融サービスの横行が後を絶ちませんが、それに加えて事業者向けに提供される違法性の高い金融サービスもここ数年で急増している傾向にあります。
中でも特に多いのが、事業資金の融資を持ちかけた悪徳・詐欺行為です。
たとえば、安い金利での借入れをチラつかせるなど、利用者に好条件を提示しながらも実際には様々な理由をつけて法外な利子を課すといったようなもののほか、契約に際して保証金の振込を強要されるといったケースもあるようです。
事業者を狙うこのような悪徳・詐欺行為の横行は今に始まったわけではありませんが、昨今続く新型コロナウイルスの感染症拡大が影響して売上が大幅に落ち込む事業者をつけ狙うかのように、以前にも増して増加のスピードが速まっていると考えられます。
金融庁や各自治体などが中心となって積極的に注意喚起を続けているものの、残念ながら一向に減少する気配はみられず、それどころか今後もますます増加の恐れがあると見込まれます。
目次
悪徳・詐欺行為を行う融資事業者の特徴や手口

では、具体的にどのような悪徳・詐欺行為を行う融資事業者が存在するのでしょうか。その特徴や手口について解説していきます。
貸金業登録番号詐欺
すでにご存知の方も多いかと思いますが、貸金業を営むにあたっては「貸金業法」に基づき、各都道府県や財務局への申請を通して貸金業登録番号を交付される必要があります。
ちなみに弊社の場合ですと、「東京都知事(3)第31521号」。
この貸金業者登録番号は、融資事業を営むうえで金融庁の監督下におかれることを意味し、同時に真っ当な融資事業者として営業を認められたことを証明する、いわば「免許証」のようなものです。
つまりHPのほか、営業DMやFAXに「安い金利で融資できる」などと勧誘があっても貸金業社登録番号を表記していない融資事業者は法律違反となる無許可・無免許で営業している悪徳業者、いわゆる「ヤミ金」であるとほぼほぼ100%の確率で断定できるわけです。
このような貸金業登録番号が無記載の融資事業者は簡単に悪徳業者であると見分けられますが、厄介なのは番号が記載されているのもかかわらず、それが架空のものである場合。
正規の表記通り「〇〇知事(1)第12×××号」や「〇〇財務局長(1)第12×××号」などと記載されているため、見ただけではその番号が実在のものか架空のものか見分けがつかないものです。
ですので、貸金業登録番号が表記されていたからといって安直に問い合わせを行うようなことはせず、まずは金融庁のHP内に設置された「登録貸金業者情報検索サービス」https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/を利用して、該当事業者の確認を行うべきだといえます。
また、中には他社の社名や登録番号を不正に表記して営業を行う融資事業者も存在します。
ですが、いくら社名や登録番号、住所等は詐称できても電話番号やFAX番号、またはメールアドレスに関しては誤魔化すことは不可能です。
したがって、「登録貸金業者情報検索サービス」で事業者の概要を確認する際には、登録番号とあわせて電話番号等が一致するかについてもチェックするべきだといえます。
HPが存在せずDM・FAX・SNSのみによる勧誘
近年では、金融機関やノンバンクを問わず、多くの融資事業者が各自のコーポレートサイトを所有しています。
また、営業活動にあたっても様々なサイトにバナー広告を掲出するといった手法が主流となっているなど、真っ当な融資事業者はネットを積極的に活用して自社サービスのアピールに努めています。
ところが、存在を公にしたくない邪な考えも持つ悪徳融資事業者は、コーポレートサイトは所有せず、web広告の掲出も控えるなど、ネットの活用を控えて、DMやFAXなどを多様して営業活動を行うという特徴が顕著にみられます。
さらに最近では、個人向けの「個人間融資」のような、主にtwitterなどのSNSにおいて同一事業者が複数のアカウントを所有し、それらを使い分けながら行われる勧誘活動だけで営業する事業者も目立つようになりました。
どちらにせよ、堂々とネット上で融資事業者としての実体を公開できない事情を抱えているのは明確であるといえることから、そのような事業者は高い確率で悪徳融資事業者と断定できるかと思います。
融資保証金の支払いを要求する詐欺行為

ここからは特に目立つ悪質な手口をご紹介します。
まずは「融資保証金詐欺」です。
これは安い金利の提示を用いて勧誘するものの、いざ契約の段階に至ると「融資保証金」や「保険料「紹介料」といった名目で金銭の支払いを要求するという行為です。
多くの場合、返済不能に陥った際の保証金であるほか、完済時に全額返却するといった説明がなされますが、たとえ支払いをしても何らかの理由をつけて結局は高金利の貸付が行われたり、最悪の場合は融資自体が実行されることな保証金を騙し取られたまま事業者に雲隠れされるといったケースも生じています。
複数の悪徳事業者が絡むシステム金融

もうひとつは、システム金融です。
システム金融は、複数の悪徳事業者がグループを結成した上で、貸付を受けた利用者を事業者間でたらい回しにし、最終的には自転車操業の状態にまで追い込む悪質な手口です。
流れとしては、まず利用者から融資の担保として小切手や手形を振り出させ、その後それらの決済が不可能に陥るようであれば、グループ内の別の事業者への借り換えを紹介し、高金利の融資に誘導するというもの。
小切手や手形の不渡りは半年で2回出すと銀行取引が停止され、事実上の倒産に至ります。
したがってシステム金融を実行する事業者は、そのような弱みを握ることにより、上記のサイクルを延々と繰り返させて金銭を巻き上げ続けるわけです。
金利が安い融資事業者が増えている 悪徳・詐欺業者にご注意!のまとめ

今回は、利用事業者に対して安い金利で悪徳・詐欺行為を行う融資事業者の特徴や代表的な手口を紹介しました。
国や自治体が注意喚起を続けるものの、悪質なサービスを提供する融資事業者は減少するどころか、昨今の不安定な社会・経済情勢に乗じるかのように増加している傾向にあります。
また今回紹介した手口にとどまらず、悪徳事業者は詐欺スキームを巧妙化させながら、あらゆる悪質な手口を用いて資金繰りにあえぐ事業者を食い物にしています。
ノンバンクの融資を利用する際には、「安い金利」などの好条件だけに惹かれて安直に申し込むようなことは避け、必ず各事業者の実体や利用者の口コミ等を事細かく調べ上げるように心がけましょう。