「金融」と「情報技術」を組み合わせ、新たな金融商品やサービスの創造を目指す動きやそれに携わる企業を指すフィンテック。
もともとはアメリカのシリコンバレーで発祥した動きでしたが、日本でもここ数年ですっかりと定着し、今では多くの金融機関やノンバンク、さらにはIT企業までがフィンテックを活用したサービスや商品の開発を積極的に進めています。
そんな注目度の高いフィンテックですが、IT分野にあまり興味のない人や苦手意識のある人であれば「自分には無縁」などと思ってしまうことも少なくないはずです。
また、複雑そうなサービスや商品を想像して、利用には少しハードルが高そうだと思う人もいることでしょう。
でも、フィンテックを活用したサービスや商品の利用には、なにも特別な知識や操作技術が必要なわけではありません。
みなさんが普段何気なく使っている金融系のサービスや商品にも、フィンテックによって開発されたものがいくつもあるのです。
そこで今回は、フィンテックによって生まれた主要な個人向けの金融サービスをご紹介するとともに、そのメリットやデメリットについても触れていきたいと思います。
目次
フィンテックの個人向け金融サービス
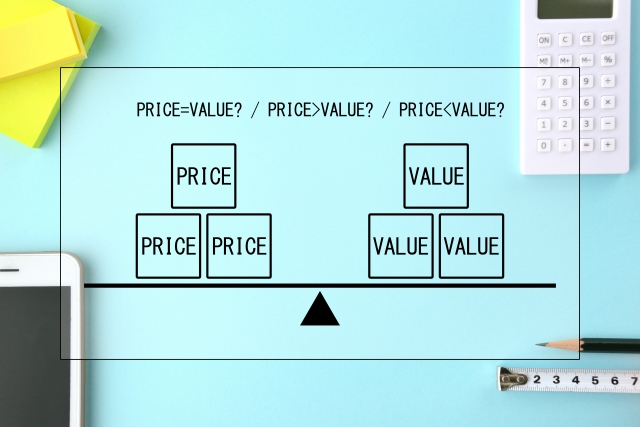
①ATMとオンラインバンキング
まずは銀行をはじめとする金融機関やコンビニに設置されるATMです。
フィンテックという動きが定着する以前から利用が続けられるATMですが、「金融」と「情報技術」を組み合わせた機器であることから、フィンテックの元祖ともいえるサービスです。
最近では、現金の引き出しや送金などの業務にとどまらず、様々な金融サービスに対応したATMが登場していることに気づいている人も多いことでしょう。
たとえば、主にセブンイレブンに設置されるセブン銀行のATMではバーコード決済の代表的なサービスであるPayPayのチャージが可能であったり、マイナンバーカードを用いての健康保険証利用やマイナポイントの申し込みは可能であったりします。
また、パソコンやスマートフォンを利用して送金や支払いを行えるオンラインバンキングもフィンテックにより開発されたサービスのひとつに数えられます。
②バーコード決済やQRコード決済
キャッシュレス決済の急速な普及によって、一気に利用率が高まったバーコード決済やQRコード決済は、フィンテックによって誕生した代表的な個人向けの金融サービスといえます。
これまでは一般的な買い物における「決済」の手段に過ぎませんでしたが、徐々にサービスの発展が進み、最近では請求書のバーコードを読み込むことで支払いが可能になる公共料金もあるなど、着実に利便性の向上が図られています。
③個人向け融資サービス
フィンテックは、資金融資サービスにも大きな変化をもたらせています。
従来の融資では、企業も個人と問わず借入先の従業員が収支状況や年収、個人情報のひとつひとつを確認して貸し出しの可否を判断していたもので、実際に現金を受け取るまでには数日の期間を要しました。
しかし、フィンテックの活用によってビックデータとAI技術を活用するAIスコアを基にした審査が可能になるなど、審査スピードを格段に向上させたサービスの提供をはじめる融資事業者が続々と登場。
貸主と借主双方の利便性と効率性を高めるサービスであることから、今後さらなる拡大が期待されます。
④利用者に最適な提案を行うロボアドバイザー
投資などの資産運用や保険選びをサポートするロボアドバイザーもフィンテックを通じて開発されたサービスです。
実際に証券会社や保険会社などを中心に、ネット上で利用者が個人の資産状況を入力したり、複数の簡単な質問に答えたりするだけで、適切な投資先や商品を提案するAIを搭載したロボアドバイザーを駆使したサービスの提供を進めています。
⑤クラウド家計簿などのPFM(個人財務管理)
PFMとは、Personal Financial Managementの略称であり、日本語に訳せば「個人財産管理」となります。
パソコンやスマートフォンに導入したPFMのソフトやアプリでは、日々の収支や資産を記録できるだけでなく、それらのデータを基にした分析や表示が可能です。
たとえば、PFMの領域で先頭を走るマネーフォワードのアプリでは、銀行口座やクレジットカードのほか、証券会社や年金資産のオンライン口座を紐づけるだけで収支や資産のデータを取得し、自動的に家計簿を作成することができます。
フィンテックの個人向け金融サービスのデメリット
 フィンテックによって生まれた個人向けの金融サービスや商品は、個人のお金の管理を劇的に効率化させるだけでなく、金融事業者の生産性の向上にもつながるなどのメリットがあります。
フィンテックによって生まれた個人向けの金融サービスや商品は、個人のお金の管理を劇的に効率化させるだけでなく、金融事業者の生産性の向上にもつながるなどのメリットがあります。
しかし一方で、いくつかのデメリットもあり、主に以下のようなものが挙げられます。
・ ネット環境は必須
・ セキュリティに不安
フィンテックは「金融」と「情報技術」に掛け合わせによる金融サービスや商品である以上、利用にあたってはインターネット環境が欠かせません。
したがって、インターネットが利用できない場所や不具合や自然災害などによって切断された場合は利用できず、緊急時に対応することが難しくなることが考えられます。
また、ネット環境に依存する以上、セキュリティ面にも不安があることから、個人情報などの管理に関しては、人手による管理よりも正確性が欠け、場合によってはネットワークを通じた流出の可能性も潜んでいます。
フィンテックによって社会的な利便性が著しく向上する一方、ユーザーがより快適かつ安全に利用できるようにするためにも、現状以上にインターネット環境やセキュリティの強化を図る必要があるといえるでしょう。















