突然ですが、皆さんは小学校・中学校・高等学校に通っていた頃、「金融」に関する授業を受けた記憶はありますか?
おそらく多くの方が、道徳の授業で「お金の価値や重要性」を、社会の授業では「市場の働きや政府の進める政策」などを学んだ経験があるかと思いますが、将来設計には欠かせない資産形成や運用、またそれらの必要性や意思決定の基本など、いわば「生活スキル」に直結する「金融の授業」を受けた経験があるという人はそう多くはないかと思います。
昨今、世界の学校教育ではそのような「生活スキル」に直結する「金融の授業」、つまり「金融リテラシー」を養うための「金融教育」が積極的に導入されており、将来に役立つ「お金との付き合い方」を子どもの頃から身につけています。
一方、日本では「金融」という言葉に対して、「生々しいお金の話は子どもの健全な発育を阻害する可能性がある」といったネガティブなイメージが染み付いていたこともあり、「金融教育」は長らく敬遠されてきた歴史があります。
しかし、金融に関する広報活動を行う金融広報中央委員会が2005年を「金融教育元年」と銘打ち、学校における金融教育の推進に重点を置いた活動を開始すると、2013年には金融庁が「生活スキルとして最低限身に着けるべき金融リテラシー」を示すなど、金融教育の本格的な導入に向けた動きが活発化。
そして「学習指導要領」の改訂を経て、小学校・中学校では2021年度から、高等学校では2020年度から、いよいよ学校教育に「金融教育」が盛り込まれることになりました。
これにより、各学校段階を通して「金融リテラシー」を養う授業がスタートしていくことになりますが、では具体的に「金融教育」とはどういった教育なのか、またどのような授業が行われるのでしょうか。
金融教育とは?

冒頭では金融教育を、資産形成や運用などの「生活スキル」に直結する「金融の授業」と簡潔に説明しましたが、日本銀行に事務局を置き、金融に関する広報活動を行う金融広報中央委員会は、金融教育を次のように定義しています。
金融教育は、お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育である。
(参照:金融広報中央員会 知るぽると)
つまり金融教育とは、単に投資手法や必勝テクニックを教え込む授業などではなく、子どもが自らお金に対して学び、考え、判断し行動に移す。
そうして金融リテラシーを養いながら将来に起こりうる問題を解決する資質や能力を磨いていく、人間教育のひとつだといえるのです。
もちろん担当教員によっては、雑談の一環として投資テクニックや経験談を紹介するような、ユーモアを交えた授業を行う場合もあるかもしれません。
ですが、金融教育を行う意義はシンプルに「お金儲け」を推進するというものではなく、あくまでも生活する上では欠かせない「お金」の使用や管理にともなう知識や判断力を身につけさせるなど、「社会で生きる力や価値観」を育むことにあるのです。
金融教育の指針となる「金融教育プログラム」

では、金融教育では具体的にどのような授業が行われるのでしょうか。
金融教育の導入とはいいつつも、従来の教科や科目の中に「金融」が加えられるわけではありません。
独立した教科として授業が進められるのではなく、従来のさまざまな教科に「金融」に関する視点や知識が織り込まれていくことになります。
そういった金融教育において指導の指針となる体系書が、金融広報中央委員会が発行する「金融教育プログラム」です。
「金融教育プログラム」では、小学校低学年・中学年・高学年・中学生・高校生の各学校段階ごとに、「生活設計・家計管理」「金融や経済の仕組み」「消費生活・金融トラブル防止」「キャリア教育」という4つの分野と達成すべき目標が設定されており、教員はそれを指針として授業を進めていくことになります。
たとえば、「消費生活・金融トラブル防止」の分野では「自立した消費者として行動するための基礎知識と態度を身に付ける」という分野目標を設定した上で、小学校高学年では家庭科の授業で「ものの選び方、買い方を考え、適切に購入する能力を身に付ける」、高校生では公民や家庭科で「環境や社会に配慮した生活が営めるようにライフスタイルを工夫する」といった年齢層別目標の達成に向けた学習指導計画を立てるといった具合です。
このように「金融教育プログラム」に記載される分野別目標や年齢層別目標は「金融教育」における重要な指針とありますが、学習指導計画が定められているわけではありません。
そのため、学校や担当教員によって授業内容に様々な工夫や個性がもたらされることが期待されています。
まとめ
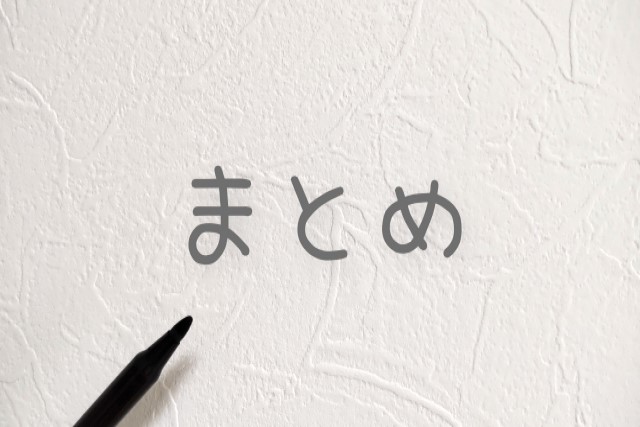
今回は、学校教育において活発化する「金融教育」について解説しました。
金融教育は、「お金」の使用や管理にともなう知識や判断力を養うことにより「社会で生きる力や価値観を育む」ための人間教育のひとつです。
小中学校では、お金の重要性や金融に関する基本的な知識を蓄え、高等学校では金融商品を活用した「資産形成」に関する内容を学習するなど、将来に向けた生活設計に不可欠となる、具体性と実用性の高い「お金の知識と判断力」、つまり「金融リテラシー」を身に着けるための教育が、いよいよ本格的に進められていきます。















